- 勤怠・給与報酬
有給休暇の法律と罰則を詳解!アルバイト・パートやフレックスタイムなど様々な場合についても解説します
2025/5/26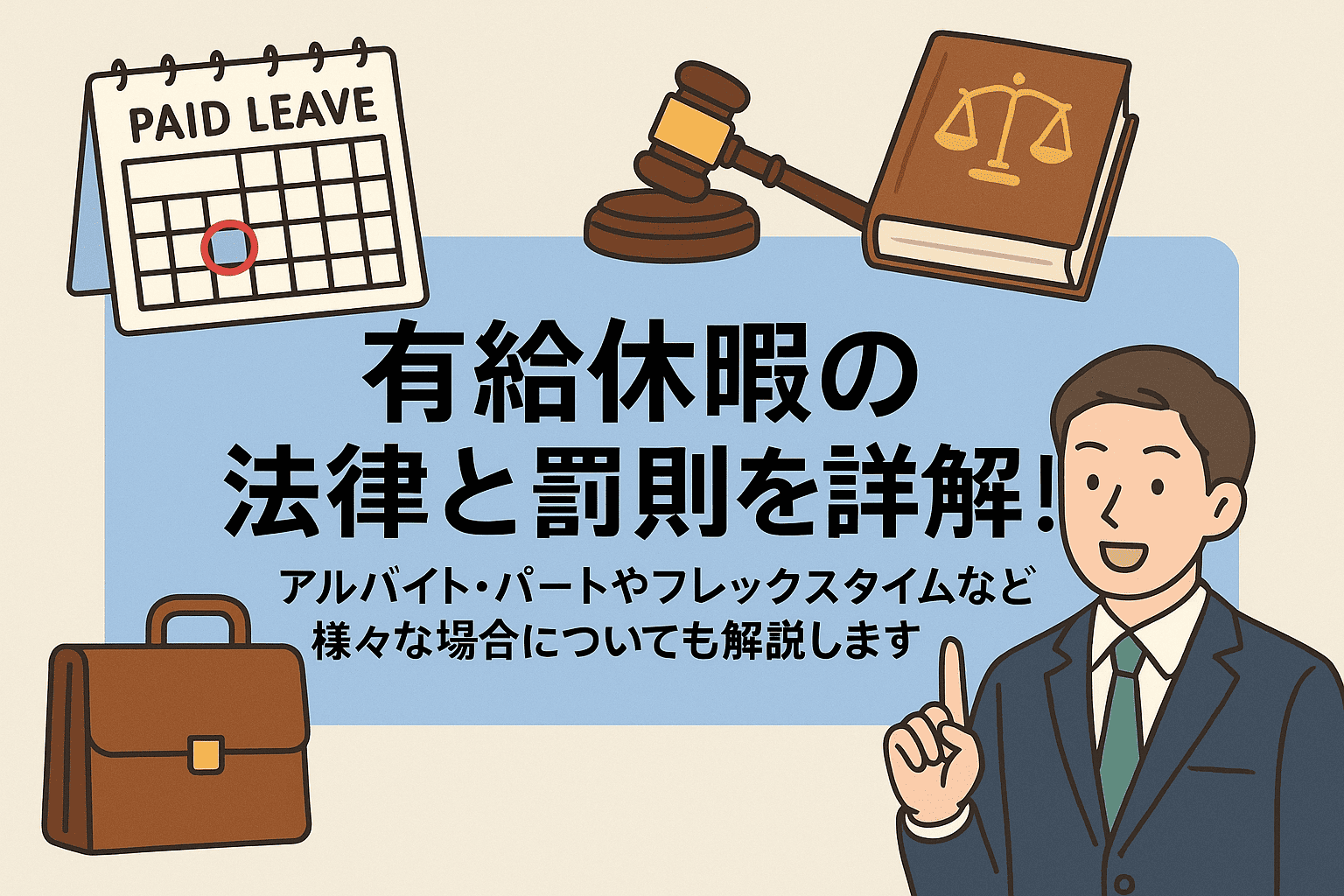
目次閉じる
有給休暇とは?基本ルールと法律の概要
有給休暇(年次有給休暇)とは、労働者が お給料をもらいながらお休みできる制度 のことなんです。日本では労働基準法第39条で定められており、正社員であろうとパートタイムやアルバイトであろうと、一定の条件を満たしたすべての労働者に与えなければならないと決められています。つまり、雇用形態や業種に関係なく、条件さえ満たせば誰でも有給休暇を取得できる権利があるんですよ。
基本ルールは2つの条件をクリアすることです。
継続勤務が6か月
入社(雇い入れ)から6ヶ月間、継続して勤務していること。
出勤率が8割以上
その6ヶ月間の「全労働日」のうち 8割以上出勤 していること(※全労働日=会社が指定した所定労働日の総数から休業日等を除いた日数です)。
この2つを満たした労働者には、会社は最低10日間の有給休暇を与えなければいけません。これは法律で義務付けられた最低日数で、実際には会社がそれ以上の日数を与えることもできます(たとえば入社時に付与する会社もあります)。有給休暇は労働者の大切な権利であり、労働者が条件を満たした時点で法律上当然に発生します。これは1973年の最高裁判決(白石営林署事件)でも示されており、有給休暇の権利は請求しなくても自動的に発生するものなんです。ですから、本来は労働者が「有給下さい」と言わなくても、権利そのものは発生しているということですね。
では付与される有給日数はどのくらいかというと、これは勤続年数に応じて段階的に増えていきます。法定の最低基準では以下の通りです。
- 6ヶ月経過(初回付与時): 10日付与
- 1年6ヶ月経過(勤続1年半): 11日付与
- 2年6ヶ月経過: 12日付与
- 3年6ヶ月経過: 14日付与
- 4年6ヶ月経過: 16日付与
- 5年6ヶ月経過: 18日付与
- 6年6ヶ月以上: 20日付与(これが法定上限)
上記は週5日勤務など通常のフルタイム労働者の場合の例です。会社はこの基準以上の日数を与えることも可能ですが、最低でもこの日数は保証しなければいけません。ちなみに付与された有給休暇は2年間有効で、使わずに残っている分は翌年度に1年だけ繰り越すことができます。しかし発生から2年を経過すると時効によって消滅 してしまうので注意が必要です(「繰り越しは1回だけ」というイメージですね)。せっかくの権利をムダにしないよう、計画的に使うことが大切ですよ。
有給休暇を実際に取得(お休み)する日の決め方にもルールがあります。原則として、「有給をいつ取るか」は労働者の請求によって決まります。働く人が「〇月〇日に休みたいです」と指定したら、会社(使用者)はその日を有給休暇として与えなければなりません。ただし例外として、もしその人が希望した日にみんな一斉に休んでしまうなど事業の正常な運営が妨げられる場合には、会社側が日程を変更する 「時季変更権」 を行使できると法律で定められています。しかしこの時季変更権が認められるのは本当にやむを得ない場合だけで、単に「会社が忙しいからダメ」という理由だけでは認められません。例えば「同じ日に多数の労働者が休暇を希望していて業務が回らない」といったケースが想定例です。要するに、労働者の有給取得の希望は最大限尊重しなければならないということですね。
また、有給休暇を取得したことによって不利益な扱いをしてはならないという決まりもあります。有給を使った人に対して「昇給や賞与でマイナス評価をする」「有給を取るなんて協調性がないと叱る」なんてことをすれば、これは労働基準法附則136条違反となります。もちろん有給を取得した日そのものは働いていない日ですが、そのことで基本給や手当を減額するようなことも認められません。有給は労働者の正当な権利ですから、気持ちよく休んでもらえるように会社も配慮が必要なんですよ。
まとめると、第1章では「有給休暇は全ての労働者に認められた大事な権利」であり、「6ヶ月勤務・8割出勤」で10日からスタートし、勤続に応じて増える」、「取得日は労働者の希望が原則で、会社はよほどのことがない限り拒めない」、そして「取得による不利益は禁止」という基本ルールを押さえてくださいね。これが有給休暇制度の土台となる考え方です。
有給休暇の取得義務化と罰則
さて、2019年の法改正(いわゆる働き方改革関連法)によって有給休暇の「取得義務化」というルールが追加されたのをご存知でしょうか?これは労務担当者なら絶対に押さえておきたい重要ポイントです。簡単に言うと、「ある程度有給休暇を持っている人には、毎年最低5日は有給を取らせないといけない」という義務が会社に課せられたんです。
具体的には、年次有給休暇が年間10日以上付与される労働者(管理職も含みます)については、そのうち5日については会社が毎年確実に取得させなければならないと定められました。これは労基法39条7項に新設された規定で、2019年4月1日から施行されています。ですからフルタイムの社員で半年後に10日もらえる人はもちろん対象ですし、パートタイムでも後述するように勤続年数によって10日以上の有給が付与される人には同じルールが適用されます。
「取得義務化」とは、労働者が自分から5日取るように “促す” だけでは足りず、会社が主体的に5日間を確実に休ませる義務 を負うという意味です。仮に本人が「自分は忙しいので有給はいりません」と言ったとしても、それでは法律違反になってしまいます。今まで有給取得は労働者任せな面もありましたが、法改正により 会社側に「最低5日は休ませる責任」がある と明確化されたわけですね。これは日本の有給取得率があまりにも低いことへの対策でもあります。政府も2025年までに取得率70%以上を目標に掲げており、企業に対して「計画を立てて有給を使わせること」「必要な人員配置をしてでも取得率を上げること」など積極的な取り組みを求めています。
では会社は具体的にどう対応すれば良いのでしょう? 基本的な流れとしては以下のようになります。
労働者による有給申請の機会提供
まず従業員自らが5日以上の有給を消化できるよう、日頃から有給取得を奨励します。年度の前半で計画的に取得するよう働きかけるのが望ましいですね。
未取得分の把握
年度途中で「このままだと5日未満になりそうな人」がいないか、人事担当者は有給の消化状況をチェックします。後述する有給休暇管理簿できちんと残日数を管理しましょう。
会社による取得日の指定
それでも本人が自主的に5日取っていない場合、会社が休む日を指定します。この際、いきなり一方的に決めるのではなく、必ず 本人の希望を事前にヒアリング してください。労働基準法では、使用者が時季指定する際には労働者の意見を聴取し、できる限り希望に沿うよう配慮する努力義務があると規定しています。「〇月〇日〜〇日に休んでくださいね」となるべく本人が休みやすい日程を一緒に考えてあげることが大切です。
時季指定の通知
本人の希望も聞いた上で会社が「この日とこの日に休んでください」と指定したら、その予定をしっかり本人に通知しましょう。口頭だけでなく文書やメールなどで記録が残る形が望ましいです。これで法律上は会社の義務を果たしたことになります。
こうしたステップを踏んで、必ず年5日以上の有給休暇を消化させることが会社の責任となりました。これを怠るとどうなるか…罰則があるんです。
労働基準法では、有給休暇に関する規定(第39条)に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。有給を与えていなかったり、5日取得させていなかったりすると、この罰則の対象になり得るわけです。第39条違反は労基法第119条で他の重大な違反行為と並んで刑事罰の対象と定められています。実際に「有給を取らせなかった」ということでいきなり逮捕者が出るケースは多くないかもしれませんが、労働基準監督署の調査が入った場合には是正勧告や指導の対象となりますし、悪質だと判断されれば送検・起訴ということもありえます。
また、第1章でも触れましたが、有給取得の申し出を会社が不当に拒否したり、取得した人を不利益に扱ったりすることも法律違反です。これも広い意味で有給休暇の権利侵害となり、罰則の適用対象となり得ます。「有給を取らせない」「有給を取った人を降格する」などは絶対にNGです。
さらに2019年の改正では、企業に「年次有給休暇管理簿」を作成・保存する義務も課されました。各従業員について有給の付与日、付与日数、取得日数、残日数、取得の時季(いつ取得したか)などを記録して3年間保存しなければなりません。この管理簿が不備だったり未作成だったりすることも法令違反となります。罰則としては同様に30万円以下の罰金等の対象となり得ますので、いい加減にせずきちんと管理しましょう。
以上が有給休暇の取得義務化とそれに伴う罰則の概要です。要は、「10日以上有給がある人は毎年最低5日は休ませる。それが会社の法的義務」であり、「違反すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金などペナルティ」があるということです。人事・労務担当者としては、この義務を確実に履行できるよう社内で体制を整える必要がありますね。
アルバイト・パートの有給休暇の取り扱い
「有給休暇って正社員のための制度でしょ?アルバイトやパートには関係ないんじゃないの?」――いいえ!そんなことはありません。アルバイト・パートの方にも有給休暇は法的に認められた権利なんです。一般には誤解されがちですが、労働基準法第39条は雇用形態によって差別はしていません。先ほど述べた 6ヶ月継続勤務と8割以上出勤という条件を満たせば、週1日しか働かないアルバイトさんであっても有給休暇は付与されます。
ただし、勤務日数や労働時間が正社員より少ない短時間労働者(パートタイマー・アルバイト)の場合、付与される有給日数は正社員と比べて比例的少なくなります。これを「比例付与」といいます。週の所定労働日数が少ない分、法定の日数も調整される仕組みです。
具体的には、労基法39条の付与日数表には週所定労働日数別の区分があります。代表的な例を挙げると、
週4日勤務(年間所定労働日数169~216日程度)の場合
初回6ヶ月経過時の付与は7日となります(正社員の10日より少ないですが、これが比例付与です)。その後も勤続年数に応じて、1年6ヶ月で8日、2年6ヶ月で9日…と増えていき、6年6ヶ月以上で最大15日になります。
週3日勤務(年間121~168日程度)の場合
6ヶ月経過時は5日付与されます。1年6ヶ月で6日、その次の年も6日、3年6ヶ月で8日…と推移し、6年6ヶ月以上で11日が付与されます。
週2日勤務(年間73~120日程度)の場合
6ヶ月経過時3日、1年6ヶ月で4日、2年6ヶ月でも4日、…6年6ヶ月以上で7日といった具合です。
週1日勤務(年間48~72日程度)の場合
6ヶ月経過時1日、1年6ヶ月で2日、その後も最大で3日までとなります。
このように所定労働日数が少ないほど付与日数も少なく設定されていますが、大事なのは「日数が少なくても有給休暇の権利自体はちゃんとある」ということです。アルバイトやパートの方でも遠慮なく有給休暇を申請できますし、会社側も正社員と同様に扱わなければなりません。「パートだから有給なし」なんてことを言うと法律違反になりますので注意してくださいね。
また、アルバイト・パートであっても勤続年数が長くなり付与日数が10日以上になれば、第2章で述べた年5日の取得義務化の対象になります。週所定4日勤務の方なら勤続3年6ヶ月で10日に達しますし、週3日勤務でも勤続3年6ヶ月で8日、4年6ヶ月で9日、5年6ヶ月で10日となります。そのため、パート社員でも長期間勤務している方については、会社は毎年5日以上の有給取得を確実にさせる義務が出てくる場合があります。この点も「パートだから関係ない」と見落とさないようにしましょう。
なお、短時間労働者の有給付与条件の計算では「週所定労働日数」を基準にしています。仮に週の労働時間が短くても、週に5日勤務していれば正社員と同じ日数が付与されます(例:1日4時間の時短勤務で週5日働く人などは日数上はフルタイム相当として扱われます)。逆に週の勤務日数が一定でないシフト制の場合は、概ね年間の所定労働日数で判断します。人事担当者としては各従業員の契約上の所定労働日数を把握しておき、それに応じた有給日数を正しく付与することが求められます。
要点をまとめると、アルバイト・パートにも有給休暇は当然に与えられるし、付与日数は勤務日数に比例して定められているということです。正社員以外の従業員にも公平に、有給休暇の申請・取得の機会を提供してくださいね。
フレックスタイム制と有給休暇の関係
最近はフレックスタイム制を導入している企業も増えています。では、フレックス勤務の社員が有給休暇を取る場合、扱いは何か特別に違うのでしょうか?結論から言えば、フレックスタイム制でも有給休暇の基本ルールは同じです。条件を満たせば日数が付与されますし、取得の権利や会社の義務も通常通り適用されます。
ただし、フレックスならではの労務管理上のポイントがいくつかあります。フレックスタイム制では、日によって働く時間が労働者の裁量に任されていますが、有給休暇を1日取得した場合にはその日は働いていなくても所定の労働をしたものとして扱う必要があります。具体的には、労使協定であらかじめ定めた「標準となる1日の労働時間」分をその日に労働したものとみなす取り扱いをします。例えば、フレックスの清算期間における1日の標準時間を8時間と決めている場合は、有給で休んだ日は8時間働いたものとして計算するわけです。これによって、フレックスの清算期間の総労働時間に不足が出たり、逆に残業時間の算定がおかしくなったりしないよう調整します。
少しややこしいですが、要するにフレックスでも「1日有給を与える」ということは、その日の労働義務8時間(標準時間分)を免除してお給料もカットしないということなんです。有給休暇は「本来働くべき日・時間の労働義務を免除して有給で休ませる制度」なので、フレックスであろうと原則は同じなんですね。
フレックスタイム制下ではコアタイム(必ず勤務すべき時間帯)がある場合とない場合がありますが、有給取得日にコアタイムが含まれていてももちろん休めます。その日は全体がお休み扱いになります。また、有給取得日は実労働時間には含めません。ですから、その日に働かなかった分を他の日に埋め合わせる必要はありませんし、逆にその日が休みだったからといって清算期間内の総労働時間が減った扱いにもなりません。「休んだけど働いたものとして扱う」というと変な感じですが、フレックスではそうしないと清算期間の計算が合わなくなってしまうための措置です。
会社としては、就業規則や労使協定の中で「標準となる1日の労働時間は◯時間」と明記しておくことが重要です。これがないと有給取得時の給与計算があいまいになってしまいます。また、フレックス社員にも有給の申請・承認ルール(事前申請何日前まで、とか、半日単位の申請可否など)を通常の社員と同様に周知しておきましょう。フレックスだからといって「有給は適当に自己申告で」としてしまうと、管理簿上も管理しづらくなりますので、他の従業員と同じように扱うのが原則です。
半日有給や時間単位の有給もフレックスタイム制の社員に適用可能です。フレックス勤務だからダメということはありません。会社が半日年休や時間単位年休の制度を導入していれば、フレックスの人もそれを利用できます。たとえば「午前中だけ有休」「2時間だけ遅れて出社」といった使い方も、所定の手続きやルールに沿っていればOKです。時間単位年休は法律上、1年間で5日分(40時間相当)までと上限が決まっていますが、これもフレックス社員に対して適用除外されるものではありません。2025年現在、時間単位年休の上限緩和の議論もなされていますが(上限5日をもっと増やそうという動き)、現時点では5日が限度です。自社で時間単位の有休制度を採用している場合は、この範囲でフレックスの従業員にも柔軟に取得させてあげると良いでしょう。
以上のように、フレックスタイム制でも有給休暇制度そのものは変わりませんが、休んだ日の扱い(標準労働時間分労働したものとみなす)など計算上の取り扱いを正しく行う必要があります。就業規則や勤怠システムでフレックスと有給の両方に対応できるように整備し、従業員にもルールを周知しておいてくださいね。
有給休暇取得義務化への対応策
第2章で触れた年5日の有給取得義務に対応するために、企業側では様々な工夫や制度設計が求められます。ここでは、人事労務担当者として押さえておきたい 実務的な対応策 をいくつか紹介します。
有給休暇管理簿による徹底管理
まず基本中の基本ですが、有給休暇管理簿をしっかり活用しましょう。2019年の改正以降、各企業には従業員ごとに有給の付与日・日数、取得日・日数、残日数を記録する管理簿の作成と3年間の保存が義務付けられています。エクセルや市販の勤怠管理ソフト、クラウドの人事システムなどを使って、誰が何日持っていて、何日使っていて、あと何日残っているかを常に把握できるようにしてください。管理簿が未整備だと有給の消化状況を見逃してしまい、「気づいたら義務の5日を満たせなかった…」なんて事態にもなりかねません。また管理簿の不備自体が法違反になりますので要注意です。
具体的な管理ポイントとしては、
基準日(付与日)ごとの管理
従業員それぞれに有給の基準日(初回付与日)があるので、その1年ごとに5日取得したかを見る必要があります。人によって入社日が違えば基準日もバラバラですから、一覧で管理する際は基準日別に並べるか、あるいは全社員共通の管理期間(例えば毎年4月~翌3月)に統一して付与する「一斉付与方式」を採用するのも一法です。
残日数の見える化
従業員自身にも自分の有給残が何日か、年内にあと何日取る必要があるかを知らせるようにしましょう。社内のマイページや給与明細に残日数を記載したり、定期的にメールでお知らせしたりすると親切です。
取得状況のチェック体制
管理簿は作って終わりではなく、最低でも年に数回は取得状況をチェックしましょう。例えば四半期ごとに「5日取得済みか未達か」のリストを出して、上長にアラートを上げる仕組みを作ると良いです。年末になって慌てることがないよう、早め早めの確認が肝心ですよ。
計画的付与の制度を活用
労働基準法では、有給休暇のうち5日を超える部分については労使協定を結べば計画的付与(計画年休)を行うことが認められています。これはどういうものかというと、簡単に言えば 「会社側であらかじめ有給消化の計画を立ててしまう」という制度です。年5日分は労働者の自由意志に任せなければなりませんが、それを超える有給については、例えば会社指定の一斉休業日に充てたり、部署ごとの交代休暇計画を立てたりすることができます。
計画年休のメリットは、会社主導である程度まとまった休みを設定できる点です。たとえばお盆休みや年末年始休暇の際に、有給を充当して長期休暇を構成するケースがあります。「有給休暇取得促進のための計画表」などを年度当初に作成し、各社員の協力を得ながら消化を進めていくのです。政府も有給取得率向上のために 年度当初に取得計画を作成すること を企業に推奨しています。計画的付与を活用すれば、従業員任せにせず会社として取得率向上にコミットできるので、特に有給消化が進まない職場では検討する価値があります。
もちろん計画年休制度を導入するには労使協定の締結が必要です。労働者代表や労働組合と十分話し合い、「どの部分の有給を計画的付与に充てるか」「対象社員は誰か」「具体的な取得方法(一斉付与か交替制か)」などを決めて書面で協定を結びましょう。5日分は本人の自由利用に残しておかなければならない点だけ注意してください(義務化された年5日を計画付与に含めることはできません)。
職場の意識改革と取得奨励
制度や帳簿の整備と同じくらい大事なのが、職場の有給取得に対する意識を変えていくことです。いくらルールで決めても、現場で「有給を取るなんてけしからん」みたいな空気があったら従業員は休みにくいですよね。トップダウンで有給取得を推進するメッセージを出すことも必要です。社長や管理職が「有給5日取得は絶対だから、みんな遠慮せず取ってね!」と社内報や朝礼で繰り返し伝えるだけでも、現場の心理的ハードルは下がるものです。
また、管理職自身が率先して有給を取得するのも効果的です。上司が忙しさを理由に全く休まないようだと、部下も「休みにくいな…」と感じてしまいます。逆に上司が「今月ちょっと休暇取ります。皆さんも計画立ててね」と率先してくれれば、部下も取りやすくなりますよね。「有給休暇取得促進週間」など期間を区切ってキャンペーンを行う企業もあります。
さらに、有給取得の理由を問わない風土づくりも大切です。法律上、有給を使う理由は自由なので、会社が「理由を書け」などと強制することはできません。従業員が病気療養だろうと旅行だろうと、あるいはただ家でゆっくりするだけでも、有給は堂々と使っていいんです。人事担当者としては「有給は労働者のみなさんの権利です。リフレッシュや自己研鑽など、有意義に活用してください!」と前向きにアナウンスしましょう。そうすることで「有給を取ってもいいんだ」という安心感を与え、結果的に義務の5日取得もスムーズに達成できるはずです。
半日休暇・時間休暇の導入
従業員が有給を取りやすくする工夫として、半日単位・時間単位での有給取得を制度化することも検討しましょう。法律上、有給休暇の単位は原則1日ですが、労使協定を結べば1時間単位でも取得可能です(年5日分までが上限)。半日単位については明文化された上限はありませんが、一般に午前休・午後休といった形で導入している会社が多いです。
例えば「午後に子供の学校行事があるから半休したい」「病院に行くので2時間だけ抜けたい」といったニーズは現代では珍しくありません。柔軟な単位で休める制度があれば、従業員は有給を消化しやすくなります。「丸一日休むほどではないけどちょっと用事が…」という時に時間有休が使えると便利ですよね。結果として有給取得率の向上にもつながります。
ただし、時間単位年休制度を導入する際は就業規則への明記と労使協定の締結をお忘れなく。また、「5日分まで」という上限も守る必要があります(例えば所定労働時間8時間の会社なら最大40時間分までが時間有休にできる範囲です)。この上限については将来的に緩和される可能性も議論されていますが、現行では順守してください。
有給休暇取得状況の定期チェックとフィードバック
最後に、PDCAサイクルで有給取得の管理を回すことも大事です。一度制度を作ったら終わりではなく、定期的に取得状況を分析して問題点を洗い出しましょう。部署ごと・職種ごとに偏りはないか、特定の上司の下だけ取得率が低くないか、といった点もチェックポイントです。もし偏りがあるようなら、人員配置の見直しや業務分担の改善を検討します(人手不足で休めない部署がないか等)。
フィードバックとしては、各部署の有給取得率を社内報で発表したり、管理職の評価項目に「部下の有給取得推進」が含まれている例もあります。取得しやすい職場づくりも管理職の仕事のうちですから、そうした観点で評価・指導していくのも有効でしょう。
また、労基署の動きとしては、年次有給休暇の取得状況を報告させる調査や、指導が入るケースも今後考えられます。厚労省も取得率向上に本腰を入れていますので、自社としても「常に法令順守しつつ、従業員にしっかり休んでもらう」というポジティブな姿勢で取り組んでくださいね。
以上の策を総合すれば、有給5日取得義務化にも十分対応できるはずです。「付与・管理・計画・意識改革」の4つのキーワードで備えておけば怖いものなしですよ!
よくある質問とその対応
最後に、有給休暇に関して企業の労務担当者からよく寄せられる質問と、その対応策・考え方についてまとめます。疑問を一つ一つ解消して、万全の態勢で有給管理に臨みましょう。
Q: アルバイトやパートにも本当に有給休暇を与えないといけないの?
A: はい、もちろんです。第3章で説明した通り、雇用形態にかかわらず労働基準法上認められた権利です。条件(6ヶ月勤務・8割出勤)を満たせば必ず付与しましょう。「パートだから有給なし」は違法になります。例えば週2日勤務のパートさんでも6ヶ月働けば3日の有給がもらえます。遠慮せず取得できるよう周知してあげてくださいね。
Q: うちの社員はみんな有給なんていらない、って言ってるんだけど、それでも5日取らせないとダメ?
A: ダメです。社員さんが善意で「休まなくていいですよ」なんて言っても、法律上は会社に休ませる義務があります。有給休暇は労働者の心身の健康を守るための制度なので、「休まない権利」は認められていません。たとえ本人が望まなくても年5日は必ず取得させてください。どうしても休まない社員には、会社側で休暇日を指定して与えるしかありません(その際は本人の希望も聞きつつ配慮しましょう)。
Q: 年5日の義務以外の有給は消化させなくてもいいの?
A: 法律上は「5日以上」の義務なので、それ以上について直ちに罰則があるわけではありません。しかし、有給休暇は労働者の大事な権利ですから、5日だけ取らせて後は野放し…ではなくできるだけ全ての有給を取得できるよう促すことが望ましいです。前章で紹介した計画的付与を使ったり、業務状況を調整したりして、「完全消化」を目指すのがベストですね。なお使いきれなかった分は翌年度に繰越できますが、繰越できるのは1年分だけなので、持ち越しが続いて大量に残っているような場合は計画的消化を検討しましょう。
Q: 有給休暇の繰り越しルールは?
A: 有給の有効期限は2年間です。付与された日から2年経つと権利が消滅してしまいます(労基法115条による時効)。そのため、「付与された翌年度まで」しか繰越はできません。例えば今年もらった有給は来年までは残りますが、再来年には消えます。常に最新2年分までしかストックできないので注意しましょう。ちなみに繰り越す場合も5日取得義務は毎年リセットで課されます。繰越分があっても、その年新たに付与された分が10日以上なら再び5日取得の義務対象となります。
Q: 会社が忙しい時に有給の申請を断れますか?
A: 基本的に断れません。労働者が指定した日に休まれると業務運営がどうしても成り立たない場合のみ、会社は時季変更権で別の日に変えてもらうことができます。しかし「忙しいからNG」は理由になりません。例えば「同じ日に多数の人が休む予定で代替要員も不在」といったケースでない限り、有給申請は認めるのが原則です。どうしてもその日は困る場合は、必ず代わりの取得日を提示して調整してください。「休むな」ではなく「この日は避けて別の日にしてもらえますか」という対応が必要です。
Q: 有給休暇を買い上げ(買取)したいと言われたら?
A: 在職中の有給買取は認められません。有給休暇は「休ませること」に意義があるので、会社がお金を払って休ませないというのは本末転倒だからです。労働基準法上も有給の買い上げは禁止と解されています(それを許すと制度の目的が損なわれるため)。したがって、仮に社員から「有給買い取ってほしい」と申し出があっても応じてはいけません。例外は退職が決まっている場合です。退職日までに消化しきれない有給が残っているケースでは、実務的に退職時に未消化分を買い上げ(お金で清算)することがあります。これは退職後はもう休みを取得させることができないための特例的な対応です。ただしこれも法律上の義務ではなく、会社の好意的な措置として行われているものです。基本は「在職中はしっかり休みで消化させる」、退職時にどうしてもの場合のみ検討しましょう。
Q: 管理職には有給休暇はないの?
A: 管理職にもあります。管理監督者は残業代など一部労働時間規制の適用除外がありますが、有給休暇については一般社員と同じく労基法39条の対象です。したがって条件を満たせば付与もされますし、年5日取得義務も適用されます。むしろ前述の通り、管理職こそ率先して有給を取得することで部下の手本を示していただきたいところです。「俺は有給なんかいらない」は通用しませんので、しっかり休んでもらいましょう。
Q: 有給休暇の申請方法は口頭でも良い?
A: 法律上、申請方法の定めはありませんが、できれば書面やシステム上での申請にしてください。口頭だけだと後で「言った言わない」のトラブルになりがちですし、管理簿にも記録が残りません。就業規則で「有給取得は〇日前までに所定の書式で申請すること」とルールを定めておくと良いでしょう。昨今はWebシステムや勤怠アプリでポチッと申請・承認できる仕組みも普及していますので、そういったツールの活用もおすすめです。大事なのは証拠が残る形で申請・許可を行うことです。
Q: 出勤率8割に満たない社員には有給を与えなくていい?
A: 法律上は付与しなくても構いません。労基法39条2項に「全労働日の8割未満の者には有給を与えることを要しない」とあります。たとえば欠勤や遅刻早退が非常に多くて出勤率が7割だった…という場合、次の年の有給は0日(付与なし)とすることが法的に許容されています。ただし、会社として与えてはいけないわけではありません。法定ではゼロにできるけど、会社の裁量で特別に付与することも可能です。また、出勤率計算では業務上のケガや病気で休んだ日、産前産後休業や育児・介護休業で休んだ日などは出勤したものとみなして計算する決まりがあります。これら正当な理由の休業で出勤率が下がった人は不利にならないよう配慮が必要です。総合的に判断して対応しましょう。
Q: 有給休暇を使わせない社員にペナルティを科せますか?
A: 部下が有給を取らないからといって罰を与えるのは本末転倒です。取得は労働者の権利であって義務ではありません(年5日取得させる義務は会社側の責任)なので、本人を罰する考え方はおかしいですね。むしろ有給取得を促進するのが会社の役目です。どうしても休まない社員には、上司から「有給取りなさい」と指導したり、それでもダメなら前述の通り会社指定日で強制的に休ませるしかありません。ペナルティではなく促しと制度で対応するようにしましょう。
いかがでしたでしょうか?有給休暇の基本から実務対応、最新の法律事情まで網羅して解説しました。企業の労務担当者にとって、有給休暇の適切な管理は法令遵守と従業員の満足度向上の両面で非常に重要です。ぜひ本記事の内容を参考に、自社の有給休暇運用を見直してみてくださいね。「しっかり休んでリフレッシュできる会社」は従業員にとっても魅力的ですし、結果的に生産性アップや良い人材の定着にもつながるはずですよ。
では、皆さんの職場が有給休暇をおそれず・気兼ねなく・計画的に取得できる職場になることを願っています。最後までお読みいただきありがとうございました!
- 勤怠・給与報酬


