- 勤怠・給与報酬
欠勤・勤怠不良社員への対応ガイド(正社員・フレックス・パート対応)
2025/5/26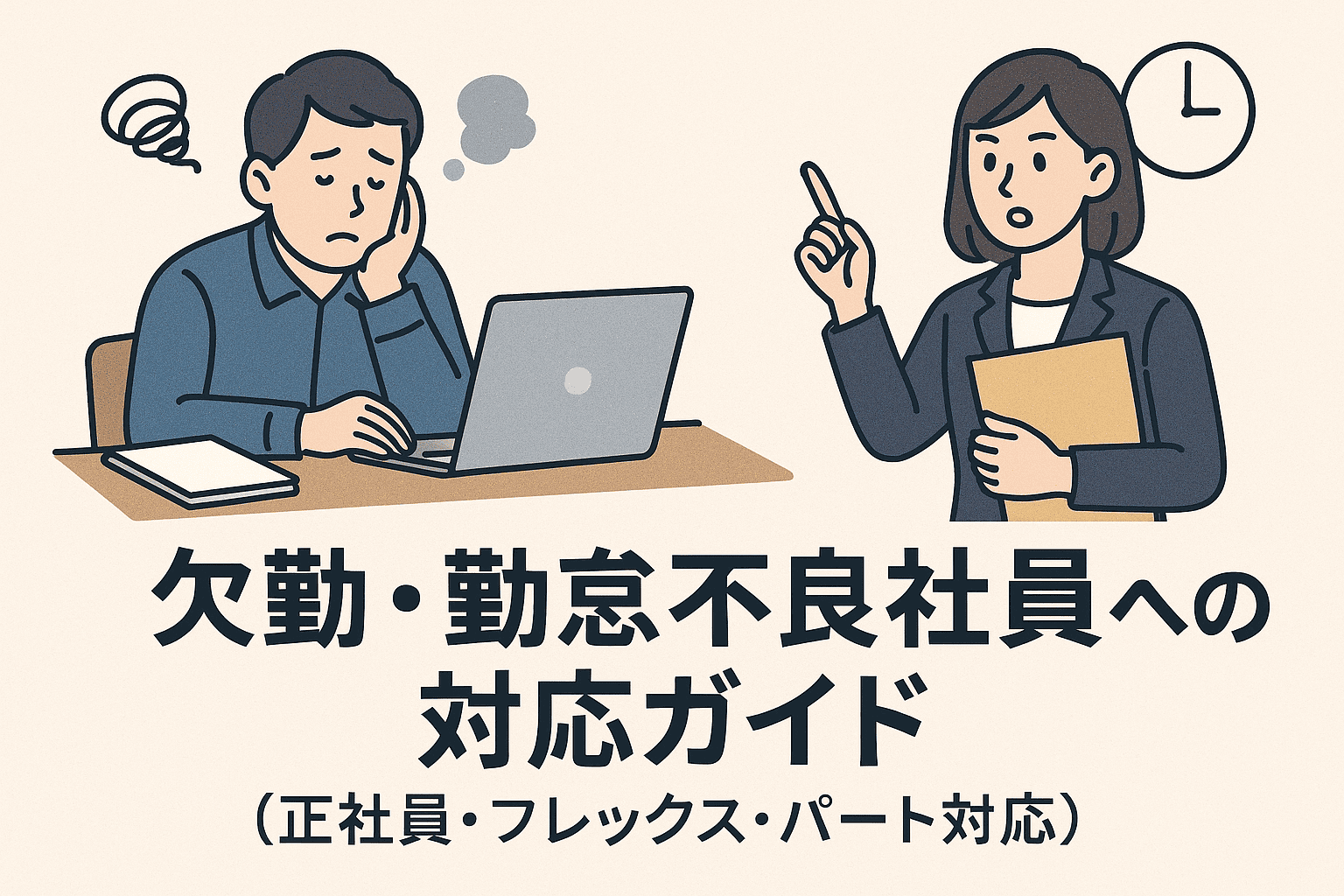
目次閉じる
- 勤怠不良とは何か?その定義と法的な位置づけ
- 欠勤者への初期対応:注意・指導と記録の徹底
- 勤怠不良による解雇は可能か?普通解雇と懲戒解雇の条件
- 退職勧奨を行う場合の注意点
- 休職命令は出せる?私傷病と業務上疾病の場合
- 休職期間満了後の対応:解雇・退職扱い・自然退職
- フレックスタイム社員の勤怠不良対応:注意点と対策
- パート・アルバイトの勤怠不良対応:正社員と何が違う?
- 勤怠不良に関する主な裁判例から学ぶ
- まとめ:適切な対応でトラブルを防ごう
勤怠不良とは何か?その定義と法的な位置づけ
勤怠不良とは、正当な理由もなく社員が繰り返し欠勤や遅刻・早退をする状態を指します。計画的な年休取得や急な家族の病気による欠勤など、やむを得ない事情による休みは含みません。勤怠不良が続くと本人への信頼が損なわれるだけでなく、職場全体の雰囲気が悪化し、同僚のモチベーション低下にもつながります。
法律上、労働者は労働契約に基づき勤務する義務(労務提供義務)があります。正当な理由なくこの義務を果たさない欠勤を繰り返すことは、契約上の重大な債務不履行(義務違反)に該当します。したがって、頻繁な無断欠勤や度重なる遅刻は懲戒処分や解雇事由になり得る行為です。ただし、日本の労働法では安易な解雇は制限されており、解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が求められます。労働契約法16条でも「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効」と定められており、勤怠不良があるからといって いきなり解雇できるわけではありません。法律の枠組みを踏まえ、適切なステップを踏んで対処することが重要です。
欠勤者への初期対応:注意・指導と記録の徹底
勤怠不良の問題が生じたら、まず初期対応として注意・指導を行い、状況の改善を図ることが基本です。欠勤が目立つ社員に対しては、ただ頭ごなしに叱責するのではなく、欠勤の理由を丁寧にヒアリングして原因を把握することから始めましょう。場合によっては、業務量が過重で体調を崩している、職場でハラスメントを受け出社が億劫になっている等、企業側の問題が背景に潜んでいるケースもあります。会社側に原因がある場合は、まず問題の解消に努め、社員への配慮やサポートを優先することが肝心です。一方、正当な理由のない欠勤であると判断できる場合は、速やかに注意・指導に移ります。
注意・指導のポイントは、単に口頭で注意するだけでなく、欠勤の事実や指導内容は必ず記録に残すようにします。具体的には、欠勤日時とその理由について本人から聞き取った内容、注意・指導した日時と内容をメモやメールで記録し保存します。これは後々状況が改善しない場合に備えた証拠になるだけでなく、本人にとっても自分の行動を振り返る材料になります。また指導の際には、欠勤が周囲に与えている影響を具体的に伝えることも重要です。「あなたの欠勤により他の社員の業務負担が増え、シフト調整や人員配置に支障が出ている」「職場の秩序やチームワークにも悪影響が出ている」といった点を丁寧に説明し、本人の自覚を促しましょう。特にパートやアルバイトの場合、自分の欠勤で自分の給与が減るだけで周囲に迷惑はかけていないと誤解している人もいます。そのような場合には、欠勤や遅刻が他の従業員にどれだけ負担を強いているかを理解させることが大切です。
さらに、欠勤の理由が健康上の問題である場合には、受診を勧めたり医師の診断書を求めたりして、健康状態の把握に努めましょう。体調不良で休みがちなら、適切な治療を受けさせることが先決ですし、勤務を続けられる状態かどうか医師の意見を確認することもできます。原因がプライベートの事情(家族の看護や介護など)であれば、必要に応じて勤務形態の見直しや有給休暇の取得促進など柔軟な対応も検討します。こうした初期対応の記録と積み重ねは、社員本人への改善機会の提供であると同時に、万一将来懲戒処分や解雇を検討せざるを得なくなった際に「会社として誠実に対応した」ことを示す重要な証跡となります。注意・指導を十分に行わずにいきなり厳しい処分に踏み切ると、後に争いになった際に「手続きが適切でなかった」と判断され、処分が無効になるリスクが高まります。
勤怠不良による解雇は可能か?普通解雇と懲戒解雇の条件
勤怠不良が一向に改善しない場合、最終手段として「解雇」を検討することもあり得ます。解雇には大きく分けて、懲戒処分として行う懲戒解雇と、通常の労働契約解除である普通解雇の2種類があります。勤怠不良の場合、状況や原因に応じてどちらの解雇事由に該当しうるか判断する必要があります。
懲戒解雇
懲戒解雇は企業秩序に著しく反する重大な違反行為に対する懲罰として行う解雇です。無断欠勤が長期間続き連絡も取れない、度重なる無断欠勤で再三の注意にも応じない、といった悪質な勤怠不良は企業の秩序を乱し業務に支障を来す重大な違反と見なされます。このような場合、就業規則の定めに基づいて懲戒解雇を検討する余地があります。懲戒解雇は労務提供義務の著しい違反に対する制裁であり、処分の中で最も重い措置です。したがって、いきなり懲戒解雇とするのは原則NGです。後述するように段階的に指導・処分を重ね、それでも改善が見られない場合に初めて検討すべき最終手段といえます。
普通解雇
普通解雇は、懲戒を伴わない通常の解雇で、会社が将来的にその従業員には労務提供が期待できないと判断した場合に行うものです。例えば、「欠勤が多く業務に支障が出ている」「正当な理由のない頻繁な欠勤により職務を全うできない」といったケースでは、労働契約上の債務不履行(契約違反)が継続し、今後も改善の見込みがないと判断されれば普通解雇の理由になり得ます。懲戒解雇のように本人の非違行為に対する制裁ではありませんが、「今後も出勤が期待できず、業務遂行が困難」と客観的に認められる場合には、雇用関係を継続し難い事由として普通解雇を検討することとなります。
解雇のハードルは非常に高いことに留意しましょう。日本では労働者の雇用は強く保護されており、解雇が有効と認められるには厳格な要件が課されています。前述の通り労働契約法16条の規定により、客観的合理的な理由と社会通念上の相当性がなければ解雇は無効となります。勤怠不良自体は就業規則上の解雇事由に該当し得ますが、それだけで即解雇が正当化されるわけではありません。裁判例でも解雇の有効性は厳しく判断される傾向にあり、「欠勤が多い」という理由だけで十分な手続きなく突然解雇すれば高い確率で不当解雇と判断されます。したがって、解雇を検討する場合でも、次章で述べるような段階的手続きを踏んだ上で、それでもなお改善の見込みがなく業務に著しい支障がある “やむを得ない場合に限る” との姿勢で臨むべきです。
なお、解雇を実行する際は就業規則や労働契約書に定められた解雇事由や手続きに則る必要があります。就業規則に勤怠不良に関する解雇事由(例:「正当な理由なき無断欠勤が○日以上続いた場合」等)があるかを確認し、無ければ安易に解雇に踏み切るべきではありません。解雇する場合は少なくとも30日前の解雇予告が法律で義務付けられており(労基法20条)、即時解雇する場合は30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要です(懲戒解雇の場合でも同様です)。懲戒解雇であっても、就業規則上「重大な背信行為の場合は即時解雇し解雇予告手当を支給しない」旨の定めがあり労基署の認定を受けない限り、予告なしに即日解雇することはできません(実際にはこうした認定が下りるケースは稀です)。要するに、どんな解雇であれ適正な手順と期間を踏む必要があるということです。
退職勧奨を行う場合の注意点
社員の勤怠不良が改善せず、しかし解雇という強制手段を取る前に、社員に自主的な退職を促す「退職勧奨」を検討するケースも多いでしょう。退職勧奨とは、会社が従業員に対し「退職したほうがよいのではないか」と持ちかけ、合意の上で労働契約を終了させる方法です。会社側から退職を提案し、従業員が了承して退職届を提出する形で進めます。解雇と異なり一方的に契約を切るわけではなく、あくまで合意退職のため、解雇のように不当解雇で訴訟を起こされるリスクを抑えて円満退社してもらえるメリットがあります。ただし、退職勧奨もやり方を間違えると退職強要(違法行為)とみなされる恐れがあるため注意が必要です。
退職勧奨の進め方と注意点
- まず、本人への切り出しは慎重に行います。面談の場を設け、プライバシーに配慮した上で「最近欠勤が多く業務に支障が出ている」と現状を伝えます。その際、勤怠不良の事実については客観的なデータを示すと本人も状況を理解しやすくなります。例えばタイムカードや勤怠記録を本人に見せながら説明すると、本人の納得を得やすいでしょう。繰り返し遅刻・欠勤している現実を数字で示すことで、「自分に非がある」という自覚を促し、合意を引き出しやすくなります。
- 決して脅したり執拗に迫ったりしないこと。退職勧奨はあくまで提案であり、本人が拒否した場合はそれ以上強要してはいけません。執拗に退職を迫れば違法な退職強要となり、会社が損害賠償責任を問われる可能性もあります。提案後、本人が迷っているようなら一定の熟慮期間を与えましょう。「〇日までに結論を聞かせてほしい」と期限を区切り、回答の強制はしないことです。
- メリット・デメリットの説明: 本人にとって退職しない場合のデメリット(今後勤務を続けても評価が下がる、配属転換の可能性等)と、退職に同意した場合のメリット(会社都合退職扱いとするので失業給付がすぐ出る、円満退社として前歴に傷が付かない等)を説明します。特に会社都合退職になれば失業保険の給付制限がなくなる点などは、従業員にとって受け入れやすい材料です。提示する条件(退職金の上乗せや残っている有給休暇の買い上げ等)があればそれも伝え、本人が前向きに検討できる材料を提供します。
- 書面の用意: 本人が退職に同意したら、退職届(辞表)を本人に書いてもらいます。可能なら退職合意書を会社と本人で交わし、退職日や退職理由(会社都合・自己都合)などを明記しておくと後々のトラブル防止に有効です。退職勧奨で合意退職した場合、離職票の退職理由欄は基本「会社都合退職」となります(会社から働きかけた退職のため)。この点も踏まえ、手続き上の確認を行いましょう。
退職勧奨は解雇よりマイルドな選択肢とはいえ、提案の仕方を誤ると紛争の火種になり得ます。特に長年勤めた社員ほど抵抗感が強い場合もありますので、相手のプライドや事情にも配慮しつつ、「最終的な判断は本人に委ねる」姿勢を崩さないことが大切です。退職勧奨に応じてもらえず状況も改善しない場合、改めて懲戒処分や普通解雇の是非を慎重に検討することになります(その際は専門家への相談をお勧めします)。いずれにせよ、退職勧奨を持ち出す段階に至る前に、可能な限り上記の注意・指導や配置転換などできる手立ては全て試みたと言える状況を作っておくことが重要です。
休職命令は出せる?私傷病と業務上疾病の場合
社員が私的な病気やケガにより長期欠勤を繰り返すケースでは、会社として「休職命令」を検討することがあります。休職命令とは、社員との雇用契約自体は維持しつつ、一時的に業務から離れさせる措置のことです。一定期間就労を免除または禁止し、その間に治療・静養させることで復職を促す目的があります。例えば「私傷病による欠勤が○ヶ月以上続いた場合に○ヶ月間の休職を命じる」といった制度です。この休職制度は法律上の義務ではなく、各社の就業規則や労働契約で定める社内制度として運用されます。したがって、休職命令を出すには就業規則にその根拠規定と対象となる条件(例:「私傷病により1ヶ月以上連続欠勤した場合」等)を整備しておく必要があります。就業規則に規定がない状態で一方的に休職を命じることはできません。
私傷病の場合
私傷病(仕事以外が原因の病気やケガ)のために長期間勤務できない社員に対しては、就業規則に基づき休職を命じることが可能です。多くの会社では勤続年数等に応じて3ヶ月~1年程度の休職期間を設け、休職中は基本的に無給としています。会社に落ち度がない私傷病の場合、休職中の給与支払い義務は通常ありません(健康保険に加入していれば「傷病手当金」により一定の収入補償を受けられます)。休職命令を出す前には必ず主治医の診断書などで「○月間の静養が必要」といった医学的根拠を確認しましょう。また、本人に対して休職制度の内容(期間やその間の待遇など)を十分説明し、納得を得ることも大切です。本人が「自分は働ける」と休職を拒否するケースも考えられますが、会社として就業規則に則った正式な休職発令を行えば労働契約上は有効です。とはいえ、無給になる不安や復職への焦りから本人が反発することも多いため、できれば本人の同意を得る形で休職に入ってもらうのが望ましいでしょう。休職を命じる場合は、書面(休職辞令)で期間と理由を明示し、休職中の連絡方法や復職可否の判断方法(主治医の意見聴取など)も取り決めておきます。
業務上疾病(労災)の場合
業務が原因で発生したケガや病気で社員が休業する場合(いわゆる労災による休業)には、法律上の特別な保護があります。労働基準法第19条では、労働者が業務上の負傷・疾病で療養のため休業する期間およびその後30日間は、解雇してはならないと規定されています。つまり仕事が原因のケガや病気で休んでいる間、会社は原則として解雇はおろか退職勧奨など事実上の退職強要も行えません。まずは労災保険による休業補償給付(給料の一部保障)が支給されるため、社員は治療に専念させます。会社として特別に「休職命令」を発令しなくても、労基法上の休業期間として扱われることが多いです。ただし、就業規則上に業務上傷病に対する休職規定を設けている企業もあります。その場合、私傷病の休職とは区別して、労災休職(期間中は基本給の一部を会社が補償する等)といった制度になっていることがあります。いずれにせよ、業務上のケガ・病気の場合は法律により手厚く身分が保障されます。会社は治癒または症状固定して復職可能となるまでは解雇できず、復職後も必要に応じて軽易業務への転換など配慮が求められます。万一、労災休業中の社員に対して違法に解雇や退職強要を行えば、不当解雇として裁判で敗訴するだけでなく労基署から行政指導・制裁を受けるリスクがあります。
休職命令はいずれの場合も就業規則の規定と適切な手続きが命です。休職発令時には必ず書面で命令を交付し、本人の同意や医師の診断書取得など丁寧な対応を心がけましょう。また、休職期間中も定期的に本人の療養状況を確認し、復職の可否について情報収集します。こうしたプロセスの積み重ねが、後述する「休職期間満了後」の対応をスムーズにし、トラブル防止につながります。
休職期間満了後の対応:解雇・退職扱い・自然退職
会社の休職制度に基づく休職期間が満了した時点で、社員が復職できない(治癒していない)場合の扱いについて解説します。この局面は非常にデリケートで、適切に対処しないと法的トラブルに発展する可能性があります。
多くの企業では就業規則に「休職期間満了時の取扱い」が定められており、典型的には「休職期間が終わっても復職できない場合は退職とする(自然退職)」または「解雇する」といった規定になっています。自然退職とは、休職期間が満了したことをもって労働契約が自動的に終了する扱いを指し、会社が解雇の意思表示をするまでもなく退職したものとみなす考え方です。一方で、規定上「解雇」としている会社もあります。いずれにせよ、休職期間満了時点で雇用を打ち切ること自体は、多くの裁判例で適法と判断されています。一定期間(例えば6ヶ月や1年など)、社員の回復を待ってもなお就業復帰できなかったのであれば、客観的に見て労働契約を継続し難い状態といえ、解雇の合理的理由があると認められるためです。実際、過去の判例でも「休職期間満了による退職扱い・解雇」は有効とされたケースが多数あります。
しかし、注意すべき例外も存在します。以下のような場合、休職満了で即退職・解雇とする処分が不当解雇と判断されるリスクが高いです。
会社側に起因する疾病の場合
セクハラ・パワハラ被害や過重労働など会社の違法行為が原因でメンタル不調に陥り休職したケースでは、単に休職期間が満了したからといって退職扱いにするのは不当と判断されます。このようなケースでは、むしろ会社側が職場環境配慮義務を怠った責任が問題であり、安易に雇用終了とせず復職支援や配置転換などで職場復帰の道を模索すべきです。
復職可能なのに復職させなかった場合
社員の主治医や産業医が「就業可能」と診断しているにも関わらず、会社が一方的に復職を認めず休職満了を迎えさせ退職扱いとした場合、裁判ではその処分が無効とされるケースが多いです。医師の復職許可=労働提供可能な状態ですから、それを無視して雇用終了とするのは合理性を欠くとみなされます。
手続き上の不備
休職命令の通知や休職期間満了の事前予告を怠った場合もトラブルになりやすいです。社員にとっては「いきなり雇用打ち切りを言い渡された」という印象となり、不信感を招きます。休職開始時に期間と満了日の説明をしていたか、満了が近い段階で本人と面談し復職可否の最終確認を行ったか、といった手続きの適正さも後々問われます。
以上を踏まえ、休職期間満了後に社員が復職できない場合は、就業規則の定めに従いつつ慎重に対応する必要があります。具体的には、休職満了時点で主治医または産業医に最終的な就労可否の判断を書面でもらい、「現時点では復職困難」という客観的証拠を確保します。その上で、就業規則所定の手続き(自然退職扱いとする通知 or 解雇通知)を正式に行います。本人への連絡はできれば対面で事情を説明し、納得を得るよう努めます。解雇とする場合は解雇予告手当の支払い等、法定の手続きも忘れずに行います。自然退職扱いとする場合でも、会社として退職日や社会保険の手続き案内など必要事項を漏れなく伝えましょう。
休職期間満了時の対応まとめ: 休職規定がある場合、「休職→復職または退職」という一連の流れが社内ルールとして整備されています。ポイントは、そのルールを適用する際に一方的・機械的に行わず、個別の事情に応じた配慮を示すことです。例えば休職期間満了間近に復職の見込みが立ってきたなら休職延長を検討するとか、仮に退職となっても復職支援の制度(一定期間内の再雇用制度等)があれば提案する、といった柔軟さも信頼確保につながります。休職期間満了で雇用を終了させるのは企業に認められた権利ですが、行使は慎重に――これがトラブル回避の鉄則です。
フレックスタイム社員の勤怠不良対応:注意点と対策
フレックスタイム制度を利用している社員の場合、勤怠管理上いくつか特有の注意点があります。フレックスタイム制は社員が始業・終業時刻を自主的に決められる制度です。そのため、「遅刻・早退」の概念が通常とは異なり、対応を誤ると社員から「制度上許されている範囲なのに不当に咎められた」と受け取られる恐れがあります。以下、フレックスタイム制における勤怠不良への対処ポイントをまとめます。
コアタイムの設定
完全フレックス(コアタイムなし)では、社員は極端な話24時間内の好きな時間に出退勤できます。その状態で「朝◯時までに出社しろ」と強制すると制度趣旨に反します。対応策として、就業規則上コアタイム(必ず勤務すべき時間帯)を設定する方法があります。例えば「10時~15時」をコアタイムと定めれば、その時間内に在席していなければ遅刻や早退とみなせます。コアタイムまでに出勤しなければ遅刻、コアタイム終了前に退勤すれば早退として扱い、必要に応じて人事考課でマイナス評価したり懲戒処分(注意・減給など)を検討できます。
コアタイムは長く設定しすぎるとフレックスの趣旨に反するとして行政通達で制限されています。「1日の標準労働時間と同じ長さのコアタイム」は認められません。適切な範囲で設定しましょう。
勤務予定時刻の申告制
コアタイムがない場合でも、社員に一日の出社・退社予定時刻を事前申告させるルールを設けることが考えられます。強制力はないものの、自己申告させることで社員の意識付けと、上司側の業務割り当て計画の参考になります。ただし、「必ず◯時までに出社すること」自体を義務付けることはできない点に留意が必要です。実際、コアタイム無しのフレックス運用下で社員に「毎朝9時までに出社する」旨の誓約書を書かせたケースでは、裁判所が「制度上9時までに出勤しなかったこと自体は非難されるべきでなく、それを理由に不利益処分するのは不当」と判断しています。したがって、あくまで自主的な目安として申告させるに留め、守れなかったからといって即懲戒としないよう注意しましょう。
評価や懲戒での対応
フレックスを悪用して極端に勤務態度がルーズな社員には、人事評価で厳正に対処することも検討します。例えば所定の総労働時間を大幅に下回っている場合や、必要な打ち合わせに常に不在で業務に差し障りが出ている場合などは、勤務態度不良としてマイナス評価を与えるのは当然です。それでも改善しない場合は懲戒処分も選択肢に入ります。具体的には、始業時間の義務はないとはいえ業務命令上「◯時からの会議には出席せよ」と指示したのに正当な理由なく欠席した、など明確な業務命令違反があれば戒告・けん責などの処分が可能でしょう。また、出退勤記録の改ざんや虚偽申告など悪質な行為があれば懲戒の対象となります。
フレックス適用除外
最終手段として、問題の社員をフレックスタイム制度の対象から除外することも検討されます。就業規則にフレックスタイム制適用者の範囲が定められている場合、人事権でその社員を通常の固定時間勤務に切り替えることが可能なケースもあります。制度適用者から外すことで、「定時始業・定時終業」を課し、通常の勤怠ルールに従わせるわけです。「フレックスだから何時に来ても自由」との甘えを許さず、改めて勤務規律を意識させる効果が期待できます。ただし、この対応は労働条件の不利益変更に当たる可能性もあるため、実施には就業規則の規定整備や社員本人への十分な説明が必要です。できれば本人の同意を得て「◯月からフレックス適用を解除し通常勤務に変更する」旨を書面で交わしておくと安全です。
以上のように、フレックスタイム制では制度の枠組みを踏まえた対応策を講じることがポイントです。単に「遅刻が多いから懲戒だ」といった短絡的な対処ではなく、まず制度面での改善(コアタイム導入等)や運用ルールの工夫で解決を図ります。それでも勤務態度が改まらなければ、評価や懲戒で処遇し、場合によっては制度適用から外す決断も必要でしょう。他の社員の士気に影響しないよう、公平な運用を徹底することが大切です。
パート・アルバイトの勤怠不良対応:正社員と何が違う?
パートタイマーやアルバイトなど非正規社員の場合でも、基本的な勤怠不良対応の考え方は正社員と共通です。無断欠勤や頻繁な遅刻があれば、まずは注意・指導を行い記録を残す、それでも改善しなければ段階的に処分を科すという流れ自体は同じです。しかし、雇用形態の違いからくる留意点もいくつか存在します。
雇用契約期間の有無
正社員(期間の定めのない雇用契約)と異なり、パートやアルバイトは有期契約の場合があります。もし契約期間が定められている場合、契約期間中に一方的に解雇することは原則できません。労働契約法17条では、有期契約の途中解約は「やむを得ない事由」がある場合に限定されています。したがって、勤怠不良を理由にするにせよ、契約満了まではまず注意・指導と配置転換などで凌ぎ、更新しない(雇止め)という形で契約を終了させるのが基本的な対応です。どうしても期間途中での解雇が必要なほど悪質(例えば連絡不能の無断欠勤が長期に及ぶ等)であれば、専門家に相談の上、法的に認められる「やむを得ない事由」に該当するか精査する必要があります。逆に雇用期間の定めがないパート社員であれば、解雇のハードルは正社員同様に厳格です。たとえ週3日勤務のアルバイトであっても、解雇が認められるための客観的合理性・社会的相当性が求められる点は変わりません。
段階的な指導と処分
パート・アルバイトだからといって、いきなり解雇して良いわけではありません。正社員以上に不真面目だから即クビ、という短絡的対応は不当解雇とされるリスクが高いです。実際の対応例として、ある社労士事務所は「度重なる遅刻・欠勤のパート社員を解雇したい」という相談に対し、注意→始末書提出→書面で警告→就業規則に基づく懲戒処分と段階を踏み、それでも改善しない場合に初めて解雇可能になるとアドバイスしています。このように、一つひとつステップを踏んで指導・戒告し、それでもダメならより重い処分へ、と漸進的に対応するのが適切です。なお、パート社員は就業規則の服務規律や懲戒規定の適用範囲に入っていない場合もあるため、事前に社内規程を確認し、必要ならパート向けの規程整備を行っておきましょう。
勤務態度への意識差
前述の通り、一部のパート・アルバイトは「自分が遅刻・欠勤してもその分給与が差し引かれるだけで会社に迷惑はかからない」と誤解しがちです。実際には突然の欠勤フォローのため他のスタッフが急遽シフトに入ったり、社員がカバーに回ったりと大きな負担がかかります。この点を本人にしっかり認識させることが重要です。指導面談では「あなたが休むことで他のパートさんや社員にこれだけ負荷がかかっている」と具体例を挙げて伝え、迷惑をかけている自覚を促します。また、体調不良が頻発する場合は医療機関の受診を勧め、健康管理を促すことも必要です。「体が弱いなら勤務日数を減らしてはどうか」など、本人の状況に応じた働き方の見直し提案も検討します。実際あるケースでは、子供の看病で欠勤が月の半分以上に及ぶパート社員に対し、勤務頻度を週1日に変更する提案を上司が行った例があります。それほど出勤率が低い場合、会社として戦力として数えるのは難しいため、一旦退職を勧めて子育てに専念してもらい、落ち着いたら再応募してもらうといった選択肢も提示されました。このケースでは「出勤率が半分以下であれば懲戒解雇も客観的に合理的理由となり得る」との指摘もあり、法的には解雇可能な水準でしたが、現実的な解決策として柔軟な提案がなされたわけです。
非正規ゆえの対応策
パート・アルバイトの勤怠不良に対しては、正社員以上にシフト調整や配置換えでの対応余地があるかもしれません。例えば他に余裕のあるパートを増員し、その人のシフトを減らす、あるいは時間帯を本人の体調の良い時間に変えてみる、といった工夫です。戦力として計算できないほど欠勤が多い場合には、契約更新を行わず円満に終了することも選択肢でしょう(この場合、契約期間満了の1ヶ月前までに更新しない旨の予告を出す必要があります)。重要なのは、非正規だからといって雑に扱わないことです。勤怠不良だからと即シフトから外したり突然契約打ち切りを通告すれば、本人はもちろん周囲の士気にも悪影響ですし、法的にも争われる可能性があります。正社員と同様の慎重さで記録と手順を踏んだ対応を心がけましょう。
勤怠不良に関する主な裁判例から学ぶ
勤怠不良を理由とする処分や解雇の適法性について、実際の裁判例もいくつか紹介します。判例に学ぶことで、どんな対応が許容され、どんな対応が行き過ぎと判断されるのかの参考になります。
高知放送事件(1977年)
民放局のアナウンサーが宿直勤務中に寝坊し、2週間で2度も放送事故(番組に穴を空ける)を起こしたため解雇された事例です。会社側は「重大な過失による懲戒解雇」に相当すると主張しました。しかし裁判所は、当該アナウンサーに職務上の責任感を欠く問題はあるとしつつも、悪意や故意によるものではなく反省の意思も示している状況でいきなり最も重い処分である解雇とするのは「苛酷に過ぎる」と判断しました。最終的にこの解雇は懲戒権の濫用(不当解雇)として無効となっています。
業務に支障を与えた重大ミスでも、一度の過誤で即解雇は行き過ぎとされる場合があります。改善の機会を与えることなく過酷な処分を科せば、裁判で覆されるリスクが高いのです。
安威川生コンクリート工業事件
ミキサー車運転手の男性が体調不良を理由に約52日間にわたり無断欠勤を続けた事例です。欠勤中、本人は自分で会社に連絡せず妻に「休む」とだけ伝えさせ、具体的な病状や治療見込みも知らせませんでした。会社が度々診断書の提出を求めても応じなかったため、ついに懲戒解雇となりました。裁判所は、「会社からの再三の指示にも従わず、長期にわたり実質的に音信不通の無断欠勤状態だった」点を重視し、この懲戒解雇は有効と判断しました。
正当な理由のない長期の無断欠勤や会社の指示命令への明確な違反がある場合、懲戒解雇が認められる可能性が高いです。特に連絡義務を怠り職場放棄に近い状況であれば、解雇もやむを得ないとみなされます。
フレックスタイム制の遅刻に関する判例
コアタイム無しのフレックスタイム制度を採用していた会社で、社員に「毎朝9時までに出社する」という誓約書を書かせていた事案です。社員が9時を過ぎて出社することが度々あったため会社は懲戒を検討しました。しかし裁判所は、「コアタイムの定めがない以上、何時に出勤しようと制度上非難されるべきでない」と指摘し、9時過ぎの出社を理由に不利益処分を与えることは不当と判断しました。
フレックスタイム制度の下では、就業規則上決まっていない時間帯の出社を一方的に「遅刻」とみなして処分することはできません。制度の設計に矛盾した指導は無効とされる恐れがあるため、ルール作りと運用を慎重に行う必要があります。
これらの裁判例から分かるように、勤怠不良への対応は一歩間違えば不当解雇や不当労働行為とみなされかねない難しい側面があります。特に解雇の判断は慎重の上にも慎重を期すべきであり、安易な決断は禁物です。一方で、社員側に明らかな落ち度や悪質性があるにも関わらず会社が適切な手続きを踏んでいれば、解雇が有効と認められるケースもあります。鍵となるのは「状況に応じた柔軟かつ段階的な対応」と「客観的な証拠の積み重ね」だといえるでしょう。
まとめ:適切な対応でトラブルを防ごう
勤怠不良の社員への対応は、経営者・人事担当者にとって頭の痛い問題ですが、正しい手順を踏めば改善の可能性を高め、最悪の事態(紛争)を防ぐことができます。まずは日頃から就業規則や労働契約で勤務態度に関するルールを明確にし、社員へ周知徹底しておきましょう。問題が発生した際は焦らず、今回解説してきたように (1)原因把握と初期対応 → (2)注意・指導と記録の積み重ね → (3)段階的な処分(戒告・減給など) → (4)最終手段としての解雇または退職勧奨 という順序を踏むことが大切です。
正社員・フレックスタイム制社員・パートタイマーといった多様な雇用形態それぞれに特有の留意点はありますが、根底にあるのは「労使双方が納得できる公正なプロセス」を経ることです。社員にとっても、自分の非が蓄積された記録や段階的指導の履歴が示されれば、解雇や退職を受け入れやすくなります。一方会社にとっても、適切な対応を積み重ねることで万一争いになっても防御の材料となります。勤怠不良への対策は即効性を求めがちですが、じっくり腰を据えて臨むことが最終的な近道です。社員が戦力として立ち直ってくれれば会社にとって大きな財産ですし、残念ながら退職となる場合でも適切な対応を行っていれば大きな揉め事には発展しないでしょう。
最後に、対応に迷ったときは一人で抱え込まず社会保険労務士や弁護士など専門家に相談することをお勧めします。法律や判例の最新動向を踏まえたアドバイスにより、会社と社員の双方にとって最善の解決策が見えてくることもあります。適切な対応によって勤怠不良問題を円満に解決し、健全な職場環境を維持していきましょう。
- 勤怠・給与報酬


