- 勤怠・給与報酬
有給休暇の「時季変更権」を正しく理解する 企業が行使できる場合・できない場合
2025/5/21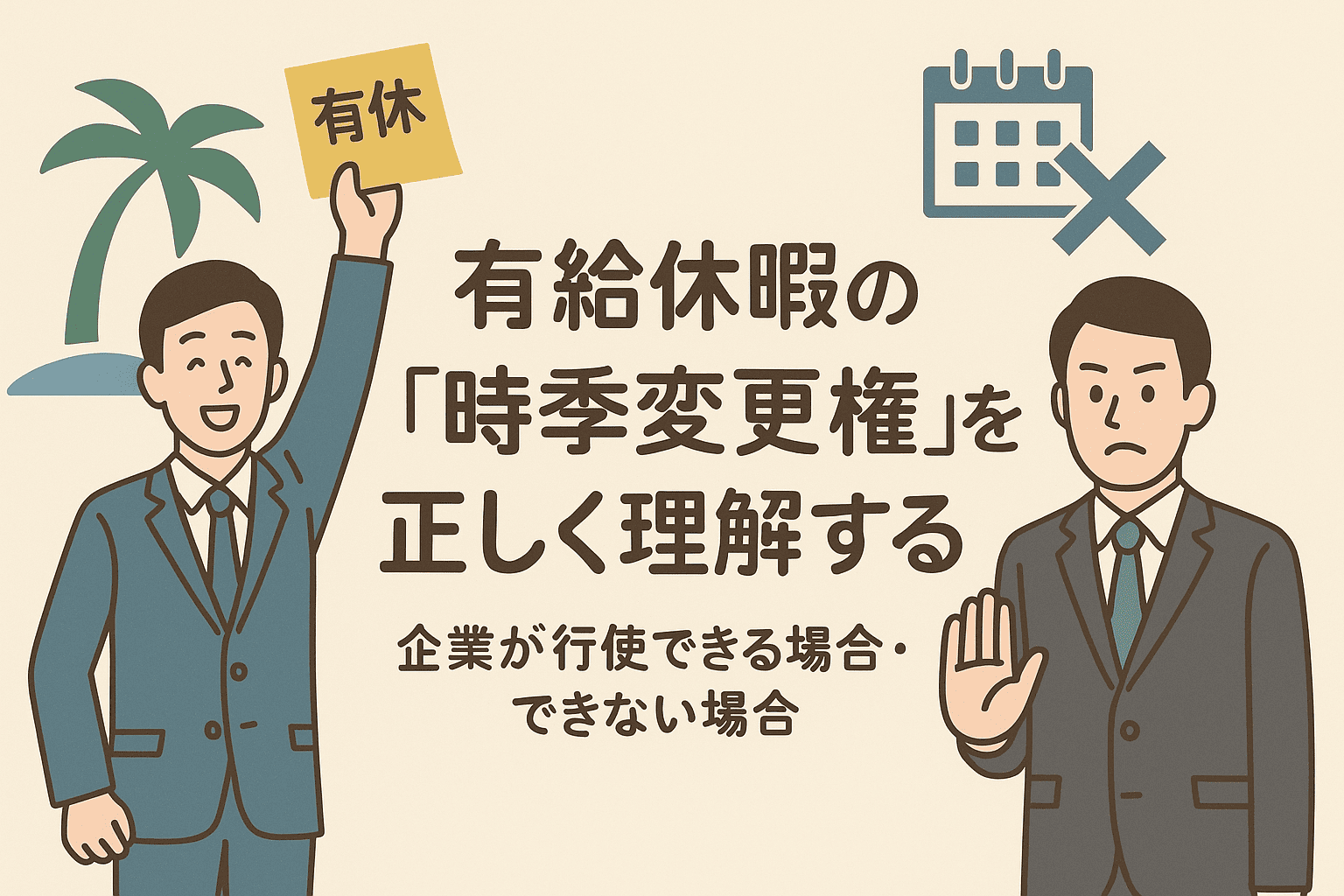
人事担当者の皆さまに向けて、有給休暇の「時季変更権」について解説します。有給休暇は労働者の大切な権利ですが、事業運営上どうしても支障が出る場合には企業側が取得時期の変更を求められる場合があります。ただし、その行使には法律で定められた厳しい条件があります。以下では、時季変更権とは何か、行使が認められるケースと認められないケース、行使する際の注意点や誤った行使のリスクについて、具体例や判例・厚生労働省の見解を交えて網羅的に解説します。最後にFAQ形式でよくある質問にもお答えしますので、ぜひ参考にしてください。
目次閉じる
- 有給休暇の「時季変更権」とは?
- 時季変更権を行使できるケース(認められる場合)
- 時季変更権を行使できないケース(認められない場合)
- 時季変更権行使時の注意点(手続き・対応・エビデンスなど)
- 不適切な時季変更のリスク(企業側のリスク)
- FAQ(よくある質問と回答)
- まとめ:正しい知識と慎重な運用の重要性
有給休暇の「時季変更権」とは?
時季変更権(じきへんこうけん)とは、労働基準法第39条に基づき企業(使用者)に認められた権利で、労働者が指定した有給休暇の時期を他の時期に変更させることができる権利のことです。通常、有給休暇を取得するタイミング(時季)は労働者が自由に指定でき、企業は原則としてその指定通りに休暇を与えなければなりません。しかし、労働者の希望する日に休暇を与えると事業の正常な運営が妨げられる場合に限り、例外的に使用者は「時季を変更する権利」を行使できます。
ここでいう「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、単に一担当部署の都合や一時的な忙しさだけでは足りず、会社全体の業務運営に具体的な支障が生じる場合を指します。判例では、企業規模や業務内容、当該労働者の職務の重要度や繁忙度、代替要員の確保難易度、休暇期間の長さなど総合的な事情から判断するとされています。その上で、企業側にはできる限り労働者の希望日に休暇を取らせるよう配慮すべき義務があると解釈されています。
例えば厚生労働省のリーフレットでも、「同じ日に多数の労働者が同時に有給休暇を希望した場合」などは事業運営上支障が出る可能性があるため時季変更権が認められることがあると説明されています。反対に、「業務が多忙だから」という理由だけでは時季変更権は認められないとも明記されています。つまり、時季変更権はあくまで法律で定められた例外的措置であり、企業が自由に有給休暇取得日を変更できるわけではありません。 なお、労働基準法第39条5項ただし書にこの規定があり、違反した場合には罰則も定められています(後述)。2019年の法改正で年5日の有給取得が企業に義務付けられましたが、この時季変更権の規定自体は以前から存在し、正しく理解して運用することが求められます。
時季変更権を行使できるケース(認められる場合)
時季変更権が行使できるのは本当に事業運営に重大な支障が出る場合に限られます。厚生労働省や裁判例で示された具体例として、次のようなケースが挙げられます。
多数の従業員が同一日に有給休暇を希望した場合
例えばお盆休みや年末年始などに社員が集中して同じ日を休暇希望すると、店舗や部署の運営に支障が出る場合があります。このように同日に休暇取得者が重なりすぎて業務が回らない場合は、企業側は時季変更を求めることが認められます。厚労省も「同じ日に多くの労働者が休暇を指定した場合」などは時季変更権行使の典型例だとしています。
重要な研修や訓練と重なる場合
従業員のスキル習得のための全社的な研修の日程と有給希望日がぶつかったケースです。特に各職場から代表者が集まるような集中研修期間で、その従業員が欠席すると研修の目的達成に支障が出るような場合には、時季変更権行使が適法と判断されることがあります。実際、最高裁判所の判例(NTT年休権事件、平成12年3月31日)でも「研修期間中に有給休暇が請求された場合、欠席によって研修成果に欠落が生じるようなときは、年休取得が事業の正常な運営を妨げるものとして時季変更権を行使できる」と判断されています。要するに、その人が休むと代替がきかず重大な支障が出る研修や訓練であれば、時季変更が認められやすいと言えます。
長期の連続休暇の申請
一度に非常に長い期間の有給休暇(例:2週間以上連続)の申し出があった場合です。企業としては長期間一人が抜けることで業務に大きな影響が出ることがあります。判例でも、報道記者が24日間連続で有給取得を申請したケースで、会社が後半10日分の有給について時季変更権を行使したことは適法と判断されています(最高裁判所判決平成4年6月23日・時事通信社事件)。この判例では最初の部分は休暇を認め、業務維持が難しい後半部分のみ時季変更を認めた点が重要です。つまり、あまりに長い連続休暇で事業運営に支障が出る部分については、必要最小限の範囲で変更を求めることが許容される場合があります。
安全・公共性の高い業務での人員確保
業務の性質上、特定の専門職が欠けると安全確保や重要インフラの運行に支障をきたす場合です。例えば新幹線の運転士など専門性が高く代替が難しい職種において、複数の乗務員が同時に休暇を取ると運行に支障が出るようなケースでは、時季変更権行使が適法と認められた裁判例があります(JR東海事件、東京高裁令和6年2月28日判決)。このケースでは会社が休暇希望日の5日前に時季変更を通告し、新幹線の安全運行に不可欠な人員を確保するためであったことなどから、裁判所は「合理的な時期の行使」であり適法と判断しました。社会的に重要なインフラ運営や安全に直結する業務では、比較的時季変更権が認められやすい傾向があります。ただしこの場合でも、企業側が平常時から適切な要員配置や代替策を講じていたか(慢性的な人手不足を放置していないか)なども考慮されます。
退職直前で業務引継ぎが必要な場合
従業員が退職前に残っている有給休暇をすべて消化しようとすると、引継ぎや業務完了が間に合わないケースがあります。一般的には退職前の有給消化は労働者の権利として尊重されますが、業務上どうしても必要な引継ぎ等が残っている場合には例外的に時季変更が認められた裁判例があります。たとえばある判例(R社事件、東京地裁平成21年1月19日判決/東京高裁平成21年10月21日判決)では、「退職にあたって不可欠な業務の引継ぎがある」という理由で退職直前の年休取得に対する時季変更権行使が有効と判断されました。ただし、このケースは極めて例外的であり、「退職前だから」という理由だけで有給取得を一律に拒否できるわけではありません。判決文でも、この事例以外に同様の判断をした例はほとんど見当たらないと指摘されています。したがって、退職前の有給消化については原則認めつつ、必要最低限の出社日について個別に相談するといった慎重な対応が望ましいでしょう。
以上のように、時季変更権が行使できるのは「このままでは仕事が回らない」という切迫した場合に限られています。企業側の都合よりも労働者の権利が基本的に優先されるため、安易な行使は認められません。次章では、逆に企業が時季変更権を行使できないケース(違法とされた例)について具体的に見てみましょう。
時季変更権を行使できないケース(認められない場合)
次のような場合、企業側が有給休暇の希望日を変更させようとしても法律上認められません。多くの裁判例や行政の見解でも、以下のケースでは時季変更権の行使は違法と判断されています。
単なる業務多忙・繁忙期であることだけを理由にする場合
「今は忙しいから休まれると困る」といった理由だけで時季変更権を行使することは認められません。会社は繁忙期であってもまず代替要員の確保など合理的な努力を尽くす義務があります。その努力もせず、ただ「繁忙期だから駄目」という抽象的理由だけでは裁判所も認めてくれません。実際に「繁忙期だが有給を認めても具体的支障が明らかでない場合」に時季変更権行使を違法とした判例があります。
業務にほとんど影響がない有給休暇の場合
たとえば繁忙期ではあってもごく短時間の有給休暇取得(半日休暇など)で代替要員を立てなくても十分業務が回るような場合です。このように有給を取っても業務に支障がない場合は、繁忙期であっても変更を命じることはできません。判例でも「忙しい時期だが短時間の休暇であり業務に支障ないケース」での時季変更権行使を違法と判断しています。要は、業務への影響が軽微なら労働者の休む権利が優先されます。
代替要員の手配など必要な努力をしていない場合
時季変更権行使には「それでもどうにもならない」という状況が必要です。実は代わりのスタッフを用意できたのに、企業がその努力を怠っていたような場合は、変更権を行使する正当性が認められません。最高裁の判例(昭和62年9月22日)でも、シフト勤務者の有給申請で代替要員の確保が可能だったのにそれをせず時季変更したケースについて、企業側の変更権行使を違法としています。したがって、企業はまず「どうにかその人が休んでも仕事が回る方法がないか」最大限検討・対応する義務があります。それを飛ばして安易に「休まれると困る」と言うのはNGです。
有給休暇の申請に対する対応が遅すぎる場合
労働者から有給の申し出があった際、企業側はできるだけ早く休暇を与えるか変更を求めるか判断する必要があります。申し出を放置した挙句、直前になって「その日は困る」と変更を求めるのは認められません。例えば休暇希望日の1ヶ月以上前に申請を出していたにもかかわらず、会社が休暇直前(3日前)になって変更を伝えたケースでは、その時季変更権行使は違法と判断されています(福岡高裁平成12年3月29日判決)。労働者としても休暇の予定を立てている可能性が高く、直前の変更要求は不利益が大きいためです。時季変更権を行使するなら速やかに(遅くとも業務上支障が判明した時点で)行う必要があります。
その他の不適切なケース
上記以外にも、「有給を取得させないための口実」と見なされるような場合は違法です。例えば「有給を使わせたくないので理由をつけて拒否する」ようなケースは論外で、時季変更権の濫用と見做されます。また、法律で定められた年5日の有給取得義務を企業が履行せず取得を妨げた場合も労基法違反となります。
以上のように、業務上の必要性が十分に説明できない場合や、企業側の準備不足・怠慢がある場合には時季変更権は行使できません。厚生労働省も「単に業務多忙というだけでは認められない」と明言しています。労働者の権利を尊重することが大前提であり、時季変更はあくまで最後の手段という位置づけです。
時季変更権行使時の注意点(手続き・対応・エビデンスなど)
企業が時季変更権を行使する際は、慎重かつ適切な手続きと対応が求められます。正当な理由がある場合でも、伝え方や対応を間違えるとトラブルに発展しかねません。以下に行使時の主な注意点をまとめます。
理由を明確に伝える
時季変更を求める際には、なぜその日に休まれると困るのかをできるだけ具体的に伝えましょう。法律上、書面などに記載する理由は簡潔な一文でも構いません(裁判例では「訓練に支障が生じるため」といった簡単な記載でも十分とされたケースがあります)。しかしトラブル防止のためには、本人への口頭説明や丁寧な説明責任が重要です。従業員が納得できるよう、例えば「その日は他に同じ資格を持つ人がいないのでお客様対応ができなくなる」等、具体的な事情を説明しましょう。理由を曖昧にすると「本当は休ませたくないだけでは?」と不信感を招きかねません。
速やかに対応する
有給の申請があったら、できるだけ早めに承認可否や時季変更の要否を判断しましょう。先延ばしにして直前になって「やっぱり休まれると困る」と伝えるのは不誠実ですし、前述のとおり裁判例でも違法と判断されています。特に、申請から希望日まで間がある場合でも油断せず、業務体制の見直しや代替策検討を早めに行い、変更が必要と分かった時点で速やかに本人へ伝えることが大切です。早めに伝えれば従業員も予定を調整しやすくなり、会社への不満も和らぐでしょう。
可能な範囲で代替案を提案する
法律上は、企業は時季変更権行使にあたり労働者へ具体的な代わりの休暇日を提示する義務まではないとされています(※最高裁昭和57年3月18日判決。「他の時季に与えることができる」と規定されているのみで、企業が日付を指定する必要はないとの趣旨)。しかし実務上は、「この日は難しいけれど翌週の◯日なら休んでも大丈夫です」などと代替日や代替策を提案する努力をすることが望ましいです。労働者としても休暇そのものが奪われるわけではなく「時期をずらすだけ」と理解しやすくなり、納得感が高まります。休暇自体は必ず他の日に取ってもらう(権利として保障する)のが企業の責任です。代替日の提案は義務ではありませんが、労使のコミュニケーション促進のためぜひ検討してください。
必要最小限の変更に留める
時季変更権を行使する場合でも、影響のある部分にだけ最小限度にとどめる配慮が重要です。例えば長期連続休暇のケースでは、前述の判例のように「全部ダメ」ではなく、支障が大きい日だけ出勤を求め、それ以外は休暇を認める対応が適切です。また、「午前中だけ出社して午後から有給にしてもらう」といった部分的な折衷案も場合によっては検討します。労働者の権利を制限するのは本当に必要な範囲内だけに留め、過度な変更要求にならないよう注意しましょう。
就業規則で手続きを定めておく
あらかじめ有給休暇の申請ルールを就業規則等で定めておくことも有効です。例えば「○日以上の連続休暇を取得する場合は1ヶ月前までに申請すること」といったルールを設定し周知しておけば、お互い計画的に対応できます。このような申請期限の定めは合理的な範囲であれば有効とした判例もあります(※電電公社此花電報電話局事件・最判昭57・3・18。「連続して3日以上の休暇取得は1ヶ月前までの届け出を要する」という就業規則の定めは合理的で有効と判断)。ただし規則に定めていても法定の権利自体を奪うことはできない点に注意してください。あくまで「事前に調整するためのルール」であり、それを理由に有給取得自体を拒否することはできません。
記録とエビデンスを残す
時季変更権を行使した場合、その経緯や理由を記録しておきましょう。具体的には、労働者からの申請日・希望日、会社側が変更を伝えた日付と方法、変更理由、代替案提示の有無、労働者の反応等をメモや電子記録で残します。万一トラブルになった際、会社が正当な理由で適切に対処した証拠となります。また、変更理由の客観的な裏付け(例えば「〇日は同部署で3人が休みを希望し、人手が1人不足する」等のデータ)があればそれも保管しておくと安心です。
従業員への配慮
休暇取得を楽しみにしている従業員にとって、時季変更の要請は少なからず負担や落胆を与えます。できる限り謝意や配慮の言葉を伝え、代わりの休暇日程も本人の希望を尊重して決めるよう努めましょう。「今回は申し訳ないけど助けてほしい。できれば◯日に振替えていただけないか」など、丁寧にお願いする姿勢が大切です。従業員も人間ですから、誠意ある対応には理解を示してくれることが多いものです。
社員が従わない場合の対応
もし企業が正当に時季変更権を行使したにもかかわらず、従業員が「納得できない」と希望日に休暇を強行した場合(出勤すべき日に無断欠勤した場合)、基本的にはその日は無断欠勤(ノーワークノーペイ)として扱うことになります。さらに企業は就業規則に従って懲戒処分を検討することも可能です。しかし、ここでも注意が必要です。後日もし裁判等で「そもそも会社の時季変更権行使が不適法だった」と判断されてしまうと、それを理由とした懲戒処分も無効となってしまいます。たとえ適法な行使だった場合でも、一日休んだだけで即解雇など過度に重い処分は裁量権の乱用とみなされ無効となる可能性があります。したがって、社員が従わなかった場合でも冷静に事態を把握し、慎重に対応策を判断することが大切です。感情的になって厳罰を科すと、後々会社側が不利になるリスクがあります。
以上のようなポイントに留意し、法律の要件を満たす場合でも慎重かつ誠実に対応することが、円満な労務管理につながります。時季変更権の行使は「最終手段」であることを念頭に、まずは労働者の希望を尊重しつつ業務との両立を図る努力を忘れないようにしましょう。
不適切な時季変更のリスク(企業側のリスク)
時季変更権を誤って行使したり、安易に有給休暇を拒んでしまった場合、企業側にはさまざまなリスクが生じます。以下に主なリスクを挙げます。
訴訟リスク・損害賠償
不当に有給休暇の取得を妨げた場合、労働者から訴訟を起こされる可能性があります。過去には、会社が時季変更権を乱用して有給取得を認めず、従業員がそれに従わなかったことを理由に解雇したケースで、解雇が不当解雇と認定され会社に600万円以上の賠償命令が下った例もあります(大阪地裁平成4年12月21日判決)。このように、企業側が敗訴すれば多額の未払い賃金や慰謝料等の支払いが発生し得ます。また裁判沙汰になることで社内外の信用失墜にもつながります。特に近年は労働者の権利意識も高まっており、訴訟に発展するケースも決して珍しくありません。
労基署への指導・是正勧告
労働者から「有給休暇を会社に不当に拒否された」と相談があれば、労働基準監督署(労基署)が調査に入る可能性があります。労基署は事実関係を確認し、違法と判断すれば是正勧告や指導を行います。最悪の場合、労基法違反として書類送検されることも考えられます。特に、2019年の法改正で年5日以上の有給を取得させることが義務づけられており(使用者による時季指定義務)、これを怠った場合や取得の妨害があった場合、行政の目も厳しくなっています。労基署から是正勧告を受けた事実が公表されたりすれば、企業イメージの低下にもつながるでしょう。
法的制裁(罰則)
年次有給休暇の権利は労働基準法で保障されており、これに違反すると刑事罰の対象となる可能性があります。労働基準法第119条では、第39条(年休規定)に違反した使用者に対し「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」を科す旨が定められています。実際に懲役刑が科されるケースは稀ですが、悪質な場合は罰金刑が科せられたり送検されることもあります。特に年5日の有給取得義務(労基法39条7項)に違反した場合も同様の罰則適用があります。法律違反は刑事責任に発展し得ることを念頭に置き、コンプライアンス遵守が求められます。
パワハラ認定リスク
時季変更権の濫用や不合理な有給休暇取得の妨害は、パワーハラスメント(権利の不当な侵害)と評価される場合があります。厚生労働省の指針でも、有給取得の妨害は職場のパワハラ行為に該当し得るとされています。例えば上司が「休みたいなんて根性が足りない」などと言って繰り返し有給申請を拒否するようなケースは、精神的な圧力を伴う不利益取扱いとしてパワハラ認定される可能性があります。パワハラが社内で問題化すれば、企業には再発防止措置義務が課されますし、被害を受けた労働者から訴訟を起こされることもあります。有給休暇取得の制限は慎重に行わないと、思わぬ角度から責任追及されるリスクがあります。
士気の低下・人材流出
法律上の問題に発展しなくても、従業員の不信感やモチベーション低下という形でリスクが現れることもあります。正当な理由なく有給を拒否されたり、休暇取得にいちいち嫌な顔をされるような職場では、社員のエンゲージメントが下がります。優秀な人材ほど権利意識が高いため、有給が取りにくい企業からは離れていってしまうかもしれません。昨今は口コミサイト等で「有給がまともに取れない会社」などと評判が広まる可能性もあり、採用面・イメージ面のマイナスにもなり得ます。
このように、不適切な時季変更権行使は企業にとって大きなリスクとなります。コンプライアンス違反による罰則や賠償だけでなく、社内の信頼関係や働きやすさの面でも悪影響があります。人事担当者としては、「有給休暇は労働者の正当な権利」であることを再認識し、安易な拒否はリスクが高いことを肝に銘じましょう。
FAQ(よくある質問と回答)
最後に、有給休暇の時季変更権に関して人事担当者が疑問に思いやすいポイントをQ&A形式でまとめました。検索ニーズの高い質問をピックアップしていますので、疑問解消にお役立てください。
Q. 繁忙期だからという理由で、有給休暇の希望日を変更させることはできますか?
A. 原則として、繁忙期という理由だけでの有給休暇の拒否・変更は認められません。労働基準法上、時季変更権が使えるのは「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られますが、単に忙しいという抽象的理由だけではこの条件を満たさないとされています。まずは他の社員との業務分担や代替要員の確保などで対応できないか検討し、それでも無理な場合に限って時季変更を検討すべきです。判例でも、「繁忙期でも具体的な支障がないなら変更権行使は違法」とされています。したがって、繁忙期だからという理由“だけ”で一律に有給取得を拒否するのは避けましょう。
Q. 退職が迫った社員が残っている有給をすべて消化したいと言っています。引継ぎが終わっていない場合でも、全部認めなければいけませんか?
A. 退職前の有給消化は労働者の権利であり、基本的には全て取得させる必要があります。業務の引継ぎなどは会社の責任で計画的に行うべきで、原則として退職直前でも有給取得を拒否してはいけません。ただし、どうしても必要な引継ぎ作業が残っており、その社員が休むと業務に重大な支障が出る場合に限り、例外的に時季変更権が認められた裁判例があります。先述のR社事件ではそれが認められましたが、このケースはかなり特殊です。一般的には退職前でも有給取得の権利は保障されます。ベストな対策は、退職が決まった時点で残り有給日数と引継ぎ計画を洗い出し、双方が納得できるスケジュールを組むことです。どうしても一部出社が必要な日があるなら、本人と話し合いの上で日程調整し、消化しきれなかった有給は買い上げ(法定範囲内で)などの検討もあり得ます。一方的に「退職前は有給消化させない」と決めるのはリスクが高いので注意してください。
Q. 従業員が有給を希望した日に、どうしても外せない重要な業務(会議や研修など)があります。この場合、時季変更権を行使してもいいのでしょうか?
A. 可能な場合があります。有給希望日と会社にとって重要な業務日程が重なる場合、その従業員が休むと業務上重大な支障が出るかどうかで判断が分かれます。例えば、全社員参加の研修や社運を左右する重要会議の日に欠員が出ると問題が大きい場合は、時季変更権を行使する正当な理由になり得ます。実際、最高裁も研修期間中の有給取得について「欠席すると研修の成果に支障が出る場合は時季変更できる」と判断しています。ただし大事なのは、「本当にその人がいないと成り立たない仕事か?」を見極めることです。他のメンバーで対応可能ならなるべく休ませてあげるべきですし、その人以外代替困難な重要業務なら前広に本人と相談し、休暇日の変更や業務日の移動など柔軟に検討しましょう。いきなり一方的に「休まないで」と伝えるのではなく、状況を説明して理解を求めることが大切です。
Q. 時季変更権を行使する際、会社側で代わりの休暇日を指定しなければならないのでしょうか?
A. 法律上は、会社が具体的な代替日を指定する義務はありません。労働基準法の規定では「他の時季にこれを与えることができる」とあるのみで、どの時季に与えるかは必ずしも会社が指定する必要はないと解されています(※判例でも会社から代替日を示す必要はないとされています)。しかし、実務上・労務管理上は代替日の提案をすることが望ましいです。代替日を提示しないと、労働者側が「いつ有給を取れるのか?」と不安になりますし、下手をすると有給の権利自体が有耶無耶になりかねません。「◯日が難しいならいつなら休めるのか」を双方で話し合い、なるべく早い時期に代替日を設定しましょう。そうすることで労働者も安心できますし、会社としても計画的に人員配置ができます。要するに、法律上の義務ではないが労使の信頼関係維持のためにはベストプラクティスと言えます。
Q. 時季変更権を行使したのに従業員が希望日に休暇を取ってしまった場合、会社は懲戒処分できますか?
A. 状況によります。まず大前提として、会社の時季変更権行使が法律の要件を満たし適法であることが必要です。適法に「その日は出勤してください」と変更を求めたのに、従業員が無断で休んだ場合、就業規則に則って懲戒処分を検討することは可能です。例えば当日の欠勤を無給扱いにしたり、注意・始末書レベルの処分を行うことは一般的には認められます。しかし、処分の重さには注意が必要です。いきなり解雇や減給など重罰にすると、たとえ時季変更が適法でも「処分が重すぎる」として無効になる恐れがあります。さらに言えば、後日その時季変更権の行使自体が裁判所で「不当(違法)だった」と判断されてしまった場合、その変更に従わなかったことを理由とする懲戒処分もすべて無効になります。ですので、まずは自社の時季変更の判断が正しかったか慎重に振り返り、正当な理由があったと確信できる場合でも、処分は段階的かつ軽微なものから検討するべきです。本人との話し合いで事情を聞いた上で、「欠勤扱いと口頭注意」程度で済ませるなど、紛争防止の観点で柔軟に対応することをお勧めします。
Q. 有給休暇の希望日を変更してもらう代わりに、その従業員に謝礼や手当を支給することは必要ですか?
A. 法律上はその必要はありません。有給休暇の時季変更はあくまで休暇の時期を後ろ倒しにするだけであり、休暇日自体は後日取得できるものです。したがって、基本的には時季変更を行っても労働者が不利益を被るわけではない(有給休暇自体は失われない)ため、追加の金銭補償等は法定されていません。ただし、企業判断で善意のフォローをすることは望ましいでしょう。例えば「急な出勤対応に対する感謝」として食事代を支給したり、代替日の有給取得時期はできるだけ本人の希望を優先する、あるいは代替日を通常より長めの休暇にしてあげる(半日有給の代わりに丸一日休みにする等)といった柔軟な対応は、従業員のモチベーション維持につながります。法律上義務ではありませんが、会社の誠意を示す意味でも検討してみる価値はあります。
上記FAQ以外にも、「計画年休との違いは?」「パートタイマーにも時季変更権は適用される?」「時季変更を伝える期限の決まりはある?」など疑問があるかもしれません。計画年休は事前に労使協定で特定日を年休取得日として割り振る制度で、時季変更権とは別物です。また有給休暇のルールはパートタイムなど雇用形態に関係なく適用されます。時季変更を通知する期限は法律上明確にはありませんが、常識的に考えてできるだけ早く伝えるのがトラブル回避の鉄則です。
まとめ:正しい知識と慎重な運用の重要性
年次有給休暇の時季変更権について、その概要から具体例、注意点まで詳しく解説してきました。最後にポイントを振り返ります。
- 有給休暇は労働者の大切な権利であり、取得時期は基本的に労働者の希望が優先されます。時季変更権は「事業の正常な運営を妨げる場合」に限って企業に認められた例外的措置です。そのため、行使場面は法律上かなり限定されています。
- 行使できるのは本当に必要な場合だけです。多数の従業員の休暇希望が重なったり、代替不可能な重要業務とバッティングした場合など、どう調整しても業務が回らない場合に限り慎重に検討します。その際も、休暇を完全に取り上げるのではなく別の日に必ず取れるよう配慮することが企業の責務です。
- 行使できないケースでは絶対に使わないこと。単なる忙しさや社内の怠慢(人手不足放置等)を理由に有給を拒否するのは違法となり得ます。「忙しいからダメ」は通用しませんので、まずは労働者の権利を尊重した運営改善を図りましょう。
- 運用時の配慮・手続きも極めて重要です。迅速な対応、丁寧な説明、代替案の提示、記録の保存など、適法な場合でもトラブルにならないようなコミュニケーションと手続きを心がけてください。従業員との信頼関係を損なわない対応が、結果的に円満な解決につながります。
- 誤った対応のリスクは大きいです。違法な有給拒否は労基法違反となり罰則の対象ですし、訴訟や労基署対応でコスト・信用を失う恐れもあります。パワハラ認定されるリスクも含め、企業にとってデメリットしかありません。「有給を取らせない」は最悪の選択肢だと心得ましょう。
結局のところ、有給休暇の時季変更権は「使わずに済む」のが理想です。企業としては計画的な人員配置や業務の平準化に努め、労働者が希望する日に安心して休暇を取れる職場環境を整えることが望まれます。その上で、どうしても避けられない場合にのみ正しい知識に基づき慎重に時季変更権を行使してください。 労働者の権利を守りつつ事業運営も維持するためには、会社と従業員の相互理解と協力が不可欠です。有給休暇の適切な管理運用によって「休みやすく働きやすい会社」を実現し、従業員のワークライフバランスと企業の安定運営の両立を目指しましょう。
参考資料:労働基準法第39条(厚生労働省 e-Gov)、厚生労働省リーフレット「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」、厚生労働省「あかるい職場応援団」サイト、最高裁判所判例集(平成4年6月23日、平成12年3月31日 他)、各種裁判例データベース、厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得ガイドライン」 等
- 勤怠・給与報酬


