
Point 1
半年以上無料で掲載可能!
採用コストの負担を最大限減らします!



目次
みなさん、こんにちは。
「アルバイト」と「パート」、よく耳にする言葉ですが、実際のところ、この二つはどう違うのでしょうか?
「同じようなものでしょ」と思っている人も多いかもしれません。
でも、実はこの二つには微妙だけど重要な違いがあるんです。
今日は、その違いの本質に迫ってみましょう。

まず、「アルバイト」と「パート」という言葉の由来から、その本質的な違いが見えてきます。
「アルバイト」はドイツ語の「Arbeit(仕事)」から来ています。一方、「パート」は英語の「Part-time(時間の一部)」の略です。
この言葉の違いが、実は両者の性質の違いを端的に表しているんです。
アルバイトは「仕事」そのものに重点が置かれています。
つまり、ある特定の仕事や業務をこなすことが主な目的なんです。
例えば、夏休み限定のリゾートバイトや、イベントスタッフなどがこれにあたります。
期間が限定されていたり、特定の目的のための仕事であることが多いんですね。
対して、パートは「時間」に重点があります。
正社員のフルタイムに対して、時間を区切って働く形態を指します。
例えば、子育て中のお母さんが、子供が学校にいる時間だけ働くようなケースです。
仕事の内容よりも、どれだけの時間働けるかが重要になってくるんです。
この違いは、雇う側と雇われる側の意識の違いにもつながっています。
アルバイトは「この仕事をやってほしい」という雇う側のニーズが強く、パートは「この時間に働きたい」という働く側のニーズが強いと言えるでしょう。

次に、アルバイトとパートでは、働く人の立場が微妙に異なります。
アルバイトは、多くの場合、その仕事が生活の中心ではありません。
学生さんが学業の合間に働いたり、別の本業を持つ人が副業としてアルバイトをしたりするケースが多いんです。
つまり、アルバイトは「プラスアルファの活動」という位置づけが強いんですね。
一方、パートは生活の一部として位置づけられることが多いです。
専業主婦(主夫)の方が家計の足しにパートで働いたり、定年退職後の方が生きがいとして働いたりするケースなどです。
パートは「生活の一部」として、より重要な位置を占めていることが多いんです。
この違いは、働く時間や頻度、そして仕事への取り組み方にも影響します。
アルバイトは比較的短期間や不定期な勤務が多いのに対し、パートはより長期的、定期的な勤務になりがちです。

アルバイトとパートでは、キャリアにおける位置づけも異なります。
アルバイトは多くの場合、キャリアの「入り口」や「お試し」的な位置づけです。
学生さんが将来のキャリアの参考にするために様々なアルバイトを経験したり、ある業界に興味があるけどまだ本格的に飛び込む勇気がない人が、まずはアルバイトから始めたりするケースが多いですね。
一方、パートはキャリアの「一部」や「延長」として位置づけられることが多いです。
例えば、子育てが一段落した主婦の方が、パートから徐々にキャリアを再開していったり、定年退職後も培った経験を活かしてパートで働き続けたりするケースがあります。
この違いは、仕事に対する責任の重さや、スキルアップの機会にも影響します。
アルバイトは比較的責任が軽く、様々な経験を積むことに重点が置かれます。
対して、パートはより責任のある仕事を任されたり、長期的なスキルアップの機会が得られたりすることが多いんです。
都道府県からアルバイトを探す(東日本)


法律上は「アルバイト」と「パート」という区別はなく、どちらも「短時間労働者」として同じ法律で保護されています。
根拠は「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」で、通称「パートタイム労働法」と呼ばれるものになります。
前述の通り、アルバイトとパートでは法律上の区別はありません。
したがって、社会保険や有給休暇といった条件は分別無く法律に従って付与されます。
日本には公的年金制度(国民年金や厚生年金保険)や医療保険制度(国民健康保険や健康保険など)のことを指し、このうち企業などで働く方が加入対象となるのが、厚生年金保険や健康保険といった「社会保険」です(厚生年金保険法 第6条・国民年金法 第2条・健康保険法 第3条)。
以下の5つを全てを満たす方が対象になります(2024年12月現在)。
対象になった方は、アルバイト・パートの区別は関係なく社会保険に加入することになります(政府広報HP:パート・アルバイトの皆さんへ)。
ただし、実際の社会保険加入率には「働き方の違い」による傾向が見られます。
パートは週4~5日、1日4~6時間程度の勤務が多く、社会保険の加入条件を満たしやすいため、加入するケースが多くなります。
一方で、アルバイトは学生や副業が多く、週2~3日勤務や短時間労働が一般的なため、加入条件を満たさないケースが多い傾向にあります。
そのため、法律上の区別はなくても、実態としてはパートの方が社会保険に加入する割合が高く、アルバイトの方は未加入のケースが多くなるのが現状です。
なお、2024年10月からは社会保険の適用拡大により、従業員数51人以上の企業で週20時間以上働く方が新たに対象となるため、アルバイトでも社会保険に加入する人が増える可能性があります。
有給休暇はアルバイト・パートの方にも付与するように法律で定められています(労働基準法 第39条)。
厚生労働省の調査によると、2022年の日本人の有給休暇取得率は62.1%であると報告しています(厚生労働省:令和5年就労条件総合調査)。
2018年の調査では、51.1%であったことから、多くの労働者は有給休暇の取得を積極的に行っていることが伺えます(厚生労働省:平成30年就労条件総合調査)。
2020年のアンケート調査で、総合求人情報サイト「はたらこねっと」に登録しているユーザーの内、アルバイト・パートで働く労働者の51%が有給休暇を付与され、8割以上の有給休暇を消化していると回答されています(ディップ株式会社:有給休暇取得についてのアンケート調査)。
しかし、実際の有給休暇の取得状況には、パートとアルバイトの働き方の違いによる傾向が見られます。
パートは比較的長期・安定的な雇用形態であり、週4~5日勤務のケースが多いため、有給休暇の付与日数が多くなり、取得しやすい傾向があります。
一方で、アルバイトは学生や副業の人が多く、短期雇用や週2~3日の勤務が一般的なため、有給休暇の付与日数が少なくなり、そもそも有給休暇を取得する機会が少ないことが考えられます。
また、アルバイトの場合は「有給休暇の制度自体を知らない」「取得しにくい雰囲気がある」などの理由で、実際に消化できていないケースもあるとされています。
そのため、法律上のルールは同じであっても、「パートのほうが実際に有給休暇を取得する割合が高く、アルバイトは取得しづらい状況がある」と言えます。
フルタイム勤務者の有給休暇日数
| 継続勤務年数 | 6ヶ月 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有給休暇日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の有給休暇日数
| 週所定 労働日数 | 1年間の 所定労働日数 | 6ヶ月 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121~120日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
有給休暇の取得方法も雇用形態関係なく共通で、職場の上司の承認が必要となります。
基本的に有給休暇の承認は通りますが、会社が有給休暇を与えることで事業の正常な運営を妨げる場合については、他の時季に与えることになっています。
また、その年で有給休暇を使い切らなくても、次年度に繰り越しができることになっています。
ただし、付与された日から起算して2年を経過すると権利が消滅します。
これらは雇用形態関係なく共通になります。
扶養控除もアルバイト・パートの区別なく適用されます。
アルバイト・パートで働く方に関して家族の扶養に入っている場合は、いわゆる「年収の壁」によって扶養から外れたりすることがあります。
以下の表を見てください。
| 年収 | 100万円以下 | 100万円超 | 103万円超 | 106万円超 | 130万円超 | 150万円超 | 201万円超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住民税の支払い | 払わない | 払う | 払う | 払う | 払う | 払う | 払う |
| 所得税の支払い | 払わない | 払わない | 払う | 払う | 払う | 払う | 払う |
| 厚生年金・健康保険の加入 | 加入しない | 加入しない | 加入しない | 条件によって加入する | 加入する | 加入する | 加入する |
| 配偶者控除 | 満額 | 満額 | 満額 | 満額 | 満額 | 段階的に減る | しない |
上記のように、年収ごとに社会保険の加入や、税負担、配偶者控除の有無といった境目があり、これを「年収の壁」と呼びます。
手取りを増やすために年収を上げても、税金や社会保険が給与から天引きされて、むしろ手取りが減るなんてこともあるため、この辺りの勤務時間調整は慎重に行う必要があります(厚生労働省:年収の壁について知ろう)。
総務省が2022年に行った「労働力調査」では、1414万人の方々がアルバイト・パートとして従事しているとしています(総務省:労働力調査)。
2017年に総務省が行った調査では、非正規労働者のうち26.2%が家族の扶養内に収めるために「就業調整」を行っていることがわかっています(総務省:平成29年就業構造基本調査)。
また、「就業調整」を行っている方の約85%が50~149万円以内で年収を調整されているようです。
1つ大事なポイントとして、調査が行われた2017年と現在を比較すると、最低賃金の全国平均が200円以上増加しているため、現在「就業調整」を行っている方はより短い時間で働いていると考えられます。
| 年 | 最低賃金全国平均 |
|---|---|
| 2024年 | 1,055円 |
| 2023年 | 1,004円 |
| 2022年 | 961円 |
| 2021年 | 930円 |
| 2020年 | 902円 |
| 2019年 | 901円 |
| 2018年 | 874円 |
| 2017年 | 848円 |
最低賃金に合わせて就業時間を減らしてしまうと、より人手不足が深刻化するというのは政府も把握しているようです。
では、パートとアルバイトでの違いはどうでしょうか?
パートとアルバイトでは、その働き方により、扶養控除の影響を受ける割合に違いが見られます。
パートは週4~5日、1日4~6時間程度の勤務が多いため、そのままであれば、年収103万円や130万円を超えるケースが多く、扶養から外れやすい傾向があります。
一方で、アルバイトは学生や副業の人が多く、短時間勤務や週2~3日勤務が一般的なため、扶養の範囲内で働きやすい(そもそも気にすることがない)特徴があります。
よって、「扶養内で働きたい」と考える主婦層が多いパートの方が、就業調整を行うケースが多いと言えるでしょう。
前述の通り、アルバイト・パートで年収を上げても「年収の壁」によって手取りが減るリスクがあり、最低賃金の上昇によって今までよりも短い時間で勤務しないといけないということがわかりました。
政府は経済対策として、「年収103万円の壁」を引き上げる政策を検討しています(首相官邸HP:2024年11月22日閣議決定)。
総務省が行った「令和4年就業構造基本調査」では、445万人が「年収の壁」の影響で就業調整を行っていると回答していることがわかりました(総務省:令和4年就業構造基本調査)。
政策はまだ検討中の段階ですが、この「年収の壁」を大きく引き上げることでアルバイト・パートの手取りを増やす目論見があります。
アルバイト・パートは手取りが増えるように、より良い労働環境が整備されていき、需要が高まっていくと予想されます。

最後に、雇う側である企業の認識の違いも見ておきましょう。
アルバイトは企業にとって「臨時的・補助的な戦力」という位置づけが強いです。
繁忙期だけ雇ったり、正社員の補助的な仕事を任せたりすることが多いですね。
つまり、企業の人員配置において、比較的融通の利く存在なんです。
一方、パートは「恒常的な戦力」として認識されることが多いです。
正社員ほどではないにせよ、ある程度継続的に働いてもらうことを前提としています。
そのため、企業はパートに対して、より長期的な視点での教育や待遇の改善を考えることが多いんです。
この認識の違いは、仕事の与えられ方や、職場での立場にも影響します。
アルバイトは比較的単純な作業や、その場限りの仕事を任されがち。
パートはより責任のある仕事や、長期的なプロジェクトに関わることも多いんです。
都道府県からアルバイトを探す(西日本)


ここまで見てきて、アルバイトとパートの本質的な違いが見えてきましたね。
大切なのは、「アルバイト」や「パート」というラベルにとらわれすぎず、自分に合った働き方を選ぶこと。
そして、選んだ後も、自分のニーズと企業のニーズがマッチしているか、常に確認しながら働くことです。
働き方は人生の大きな部分を占めます。
アルバイトとパートの違いを理解した上で、自分に合った働き方を選び、充実した人生を送りましょう。
きっと、あなたにぴったりの働き方が見つかるはずです。
この記事をシェア




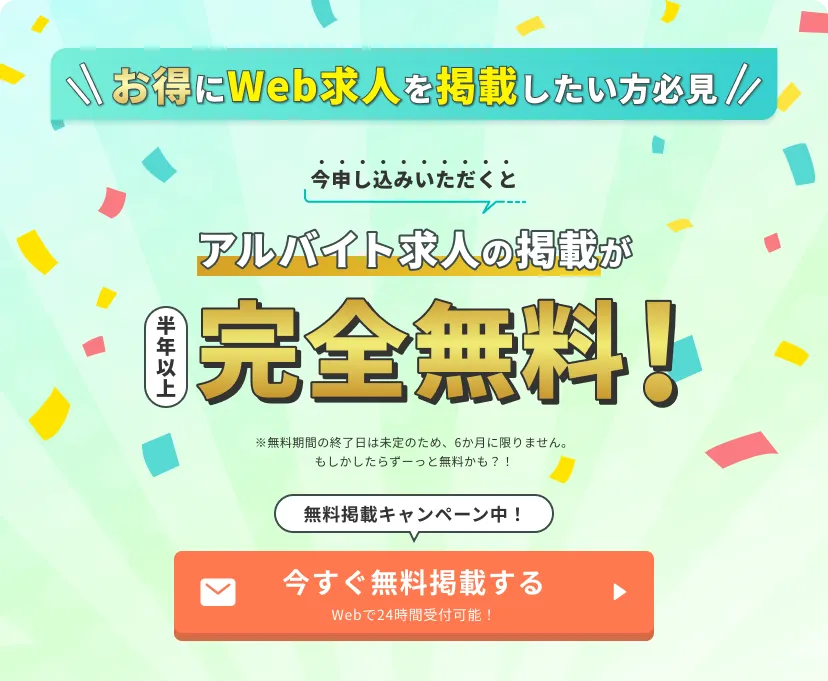
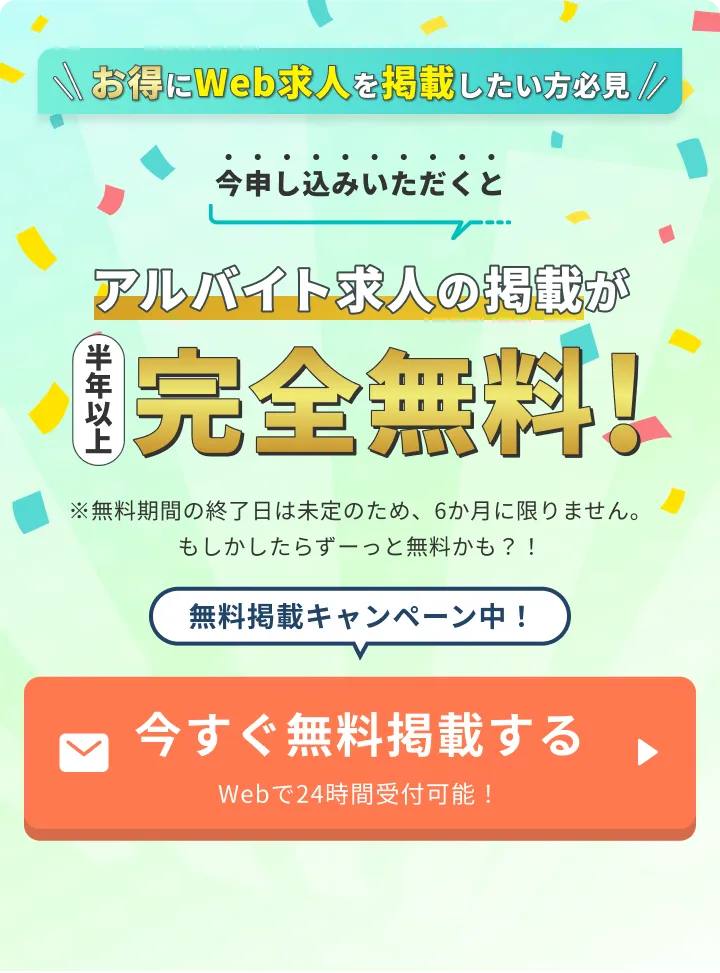




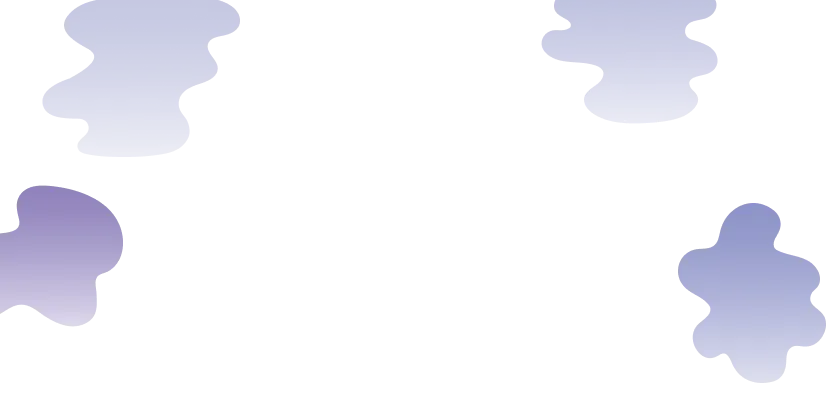
他のサイトは
掲載費用が高い
掲載しても
応募が無い
お店が忙しいので
採用の手間を減らしたい
長く続けてくれる人を
採用したい
欠員が出たので
スピーディーに
人員を補充したい
他のサイトは掲載費用が高い
掲載しても応募が無い
お店が忙しいので採用の手間を減らしたい
長く続けてくれる人を採用したい
欠員が出たので
スピーディーに人員を補充したい

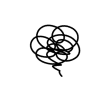

アルバイト採用のお悩み、



Point 1
半年以上無料で掲載可能!
採用コストの負担を最大限減らします!
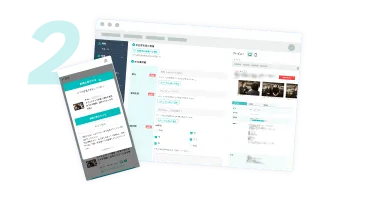
Point 2
わかりやすい管理画面でいつでも自由に求人記事を作成!
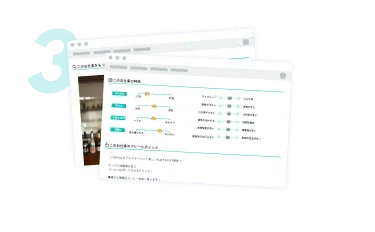
Point 3
お店の特徴や雰囲気・スタッフの人柄など、お店の魅力を多方面からアピール!
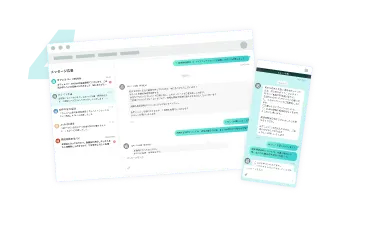
Point 4
独自のチャット機能でスムーズなコミュニケーションが可能!
お申し込み後は
すぐにご利用いただけます!
かかりません。 安心してご利用いただけます。
正社員募集もできますか?
雇用形態に関わらず、募集が可能です。
今、あるバイで求人掲載を
お申し込みいただくと
半年以上無料でご利用いただけます!
※無料期間の終了日は未定のため、 6か月に限りません。

あるバイで
バイトを探してみよう!

人気の条件から探す
都道府県を選択
条件を選択

スピード掲載可能!