
Point 1
半年以上無料で掲載可能!
採用コストの負担を最大限減らします!



目次
こんにちは!今回は、アルバイトをしている皆さんにとって気になる話題、「確定申告」についてお話ししていきます。
「確定申告って何?」「私にも必要なの?」「やらないとどうなるの?」など、疑問がたくさんあると思います。
この記事を読めば、アルバイトと確定申告の関係がスッキリ理解できるはずです!

まずは、確定申告の基本から押さえていきましょう。
確定申告とは、1年間(1月1日から12月31日まで)の収入と、それにかかる経費などを計算して、納めるべき税金の額を確定させる手続きのことです。
簡単に言えば、「去年1年間でこれだけ稼いで、これだけ使ったから、税金はこれくらいです」と国に報告することなんです。
普通、会社員の方は年末調整で税金の計算が済んでいるので、確定申告の必要はありません。
でも、アルバイトの場合は少し事情が違ってきます。どういうことなのか、詳しく見ていきましょう。

「え?アルバイトでも確定申告が必要なの?」と思った方、正解です!場合によっては、アルバイトでも確定申告が必要になることがあるんです。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
これらの条件に当てはまる場合は、確定申告が必要になる可能性が高いです。
でも、心配しないでください。
確定申告は難しそうに聞こえますが、実際にやってみると意外と簡単です。
後ほど、確定申告の方法についても詳しく説明しますね。

逆に、以下のような場合は、通常確定申告の必要はありません。
ただし、これらの場合でも、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。
特に、学生さんの場合は、確定申告をすることで思わぬお金が戻ってくることもあるんです!
都道府県からアルバイトを探す(東日本)


「確定申告って、面倒くさそう…」と思った方もいるかもしれません。でも、確定申告にはメリットもたくさんあるんです!
このように、確定申告には様々なメリットがあります。面倒くさいと思わずに、ぜひチャレンジしてみてください!

ここからは少し真面目な話になりますが、確定申告が必要なのに申告しないと、どうなるのでしょうか?
ただし、心配しすぎる必要はありません。
うっかり忘れてしまった場合などは、できるだけ早く申告すれば、大きな問題にはならないことがほとんどです。
気づいたらすぐに行動することが大切です。
都道府県からアルバイトを探す(西日本)


前章では、確定申告が必要なのに申告を行わなかった時に発生する懸念事項を列挙しましたが、この章ではより具体的な行政側の動きを基に解説していきます。
「支払調書」によって税務署は誰がどのくらい給与を受け取っているのかを把握できるようになっており、無申告者が誰であるかすぐに特定できます。
「支払調書」を企業が出さなければ良いのでは?と思う方もいるかもしれませんが、個人の所得を正しく把握し、適切に課税するために企業には「支払調書」を提出する義務があり、もし、提出しなければ、企業自身が税務署からペナルティを受ける可能性もあるため、情報を提出せざるを得ないのです。
さらに、税務署は支払調書や源泉徴収票などの情報をもとに、申告内容に不備がないかを定期的にチェックしており、申告漏れや無申告が疑われる場合には税務調査が行われることもあります。
「税務調査」とは、税務署が納税者(個人・法人)の申告内容が適正かどうかを確認する調査です。
主に、申告漏れ・過少申告・無申告・脱税の有無をチェックする目的で行われます。
税務調査には、事前に連絡がある「任意調査」と、悪質な脱税が疑われる場合に強制的に行われる「査察調査(強制調査)」の2種類があります。
通常、企業や個人事業主を対象に、税務署の職員が帳簿や領収書を確認し、申告内容に不備がないかを調べます。
調査の結果、申告漏れや不正が見つかると、不足分の税金に加え、過少申告加算税・無申告加算税・重加算税・延滞税などのペナルティ(追徴課税)が課されることがあります。
特に、意図的な脱税と判断された場合は、刑事告発されるケースもあります。
税務調査を避けるためには、日頃から正確な帳簿管理を行い、適切に確定申告をすることが重要です。また、不安がある場合は税理士に相談し、適正な対応を心がけることが求められます。
税務署は税務調査を行う前に、「事前通知」という連絡を行うことになっています(国税通則法 第74条の9)。
これは電話・書面といった手段で無申告者本人に伝えられます。
ただし、無申告の状態が悪質・証拠隠滅・以前にも無申告があったなど、税務署側で重大な懸念事項があると判断された場合は「事前通知」を行わずに直ちに税務調査が出来ることになっています(国税通則法 第74条の10)。
この「事前通知」が行われる前後、税務調査後のタイミングによって無申告加算税率は変わります。
無申告加算税とは、本来確定申告をすべき人が期限までに申告をしなかった場合に課される罰則(ペナルティ)のことです。
税務署に無申告が発覚すると、納めるべき税金に加えて無申告加算税が上乗せされ、追徴課税(ペナルティ)として支払う必要があります。
期限後申告を行うと本来納付すべき税金の他に、納付すべき税金に表記載した割合を乗じた金額の無申告加算税を加算されます。
| 期限後申告のタイミング | 収める税金が 50万円以下 | 収める税金が 50万円超~300万円以下 | 収める税金が 300万円以上 |
|---|---|---|---|
| ①事前通知が来る前に自主的に行った場合 | 5% | 5% | 5% |
| ②事前通知が来た後に行った場合 | 10% | 15% | 25% |
| ③税務調査後に行った場合 | 15% | 20% | 30% |
具体例として、下記のように無申告加算税が加算されます。
| 期限後申告のタイミング | 本来納付すべき所得税額 | 無申告加算税の割合 | 無申告加算税額の計算・合計納付額 |
|---|---|---|---|
| ①事前通知が来る前に自主的に行った場合 | 100万円だった時 | 5% | 100万円 × 5% = 5万円 |
| ②事前通知が来た後に行った場合 | 300万円だった時 | 段階的割合(5%・10%) | 50万円 × 10% = 5万円 250万円 × 15% = 37.5万円 合計 342.5万円 |
| ③税務調査後に行った場合 | 500万円だった時 | 段階的割合(15%・20%・30%) | 50万円 × 15% = 7.5万円 250万円 × 20% = 50万円 200万円 × 30% = 60万円 合計 617.5万円 |
ただし、無申告でも以下の表の条件に全て当てはまる場合は無申告加算税は課されないことになっています(国税通則法 第66条)。
| 条件 | 具体例 |
|---|---|
| 申告期限後1か月以内に自主的に申告している | 確定申告の期限から1か月以内に申告を行った |
| 期限内に申告意思があったと認められる条件を満たす | 納税を期限内に完了している(例:振替納税などを利用) 過去5年間に無申告加算税や重加算税を課された履歴がない |
延滞税は確定申告の法定申告期限(3月15日)の翌日から発生する税金です。
下記のような計算式で延滞税額が計算されます(国税庁:延滞税について)。
延滞税額=未納税額×適用利率×未納日数/365
少し複雑でわかりにくいですが、令和6年時点での延滞税の推移の具体例は以下のようになります(未納税額が10万円の場合)。
| 期間 | 適用利率 | 計算式 | 延滞税の合計納付額 |
|---|---|---|---|
| ①申告期限から1ヶ月後 | 年2.4% | 10万円 × 2.4% ÷ 12 × 1 = 200円 | 1,000円未満なので切り捨て |
| ②申告期限から2ヶ月後 | 年2.4% | 10万円 × 2.4% ÷ 12 × 2 = 400円 | 1,000円未満なので切り捨て |
| ③申告期限から3ヶ月後 | 年7.3% | 10万円 × 7.3% ÷ 12 × 1 = 608円(1か月分) 上記金額に①②の合計600円を加算する | 1,200円(100円未満は切り捨て) |
| ④申告期限から6ヶ月後 | 年7.3% | 10万円 × 7.3% ÷ 12 × 4 = 2,432円(4か月分) 上記金額に①②の合計600円を加算する | 3,000円(100円未満は切り捨て) |
無申告でも、意図的な所得隠しや偽装といった悪質な無申告と判断された場合には、無申告加算税に代わって「重加算税」を本来納付すべき所得税の40%分加算されて、支払う必要があります(国税通則法 第66条の2)。
さらに、隠蔽等を繰り返した場合は、50%にもなります(国税通則法 第66条の4)。
これはかなり大きな制裁といえるでしょう。
税務署の税務調査の結果が出た後は、その指摘どおりに申告・税納付を行う必要があります(国税徴収法 第2条)。
また、納付期限までに税務署に出向いて不足分を納付しない場合、財産の差押えなどの滞納処分が実行される可能性があります(国税徴収法 第76条)。
政府は、無申告者に対する監視を強化しています。
下記の表のとおり、毎年数千件の税務調査が行われており、積極的に調査を実施していることが伺えます。
| 事務年度 | 税務調査件数(件) |
|---|---|
| 令和元年 | 7,328 |
| 令和2年 | 2,993 |
| 令和3年 | 3,828 |
| 令和4年 | 5,229 |
| 令和5年 | 5,274 |
令和4事務年度では、1368億円もの金額が、所得税の追徴課税(加算税)で支払われたという調査結果(国税庁 令和4事務年度 所得税及び消費税調査等の状況)があり、多くの人が無申告でも結局発覚して多額の税金を支払う羽目になっています。
| 順位 | 業種目 | 1件あたりの申告漏れ所得金額【万円】 | 1件当たりの追徴税額(含む加算税)【万円】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 経営コンサルタント | 3,871 | 1,040 |
| 2 | ホステス、ホスト | 3,654 | 507 |
| 3 | コンテンツ配信 | 2,381 | 436 |
| 4 | くず金卸売業 | 2,068 | 683 |
| 5 | ブリーダー | 2,028 | 459 |
| 6 | 焼き鳥 | 1,657 | 427 |
| 7 | 太陽光発電 | 1,625 | 119 |
| 8 | 内科医 | 1,621 | 408 |
| 9 | スナック | 1,616 | 326 |
| 10 | 西洋料理 | 1,517 | 288 |
(参考:令和5事務年度 所得税及び消費税及び消費税調査等の状況|国税庁)
税務署は、「申告漏れが発生しやすい業界」「不正が多い業界」に重点的に税務調査を行います。
以下のような業界特性があると、税務調査のターゲットになりやすくなります。
特に、飲食業・美容業・建設業・ナイトビジネスは、売上の一部を抜く(売上除外)、架空経費を計上する、不正な給与処理をするといった手口が過去の税務調査で多数発覚しているため、重点的に調査が行われています。
国税庁が公表している「令和5事務年度 法人税等の調査事績の概要」によると、令和5事務年度における法人(企業)に対する実地調査件数は59,000件であると報告されています。
一方、個人事業主やフリーランスに対する所得税の実地調査件数は、「令和5事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によれば、47,528件と報告されています。
これらのデータから、法人の実地調査件数の方が個人よりも多いことがわかります。
これは「企業を調査すると、大きな税金を回収できるため、税務署にとっては効率がいい」ということがあるかと思います。
ただし「個人事業主でも、不自然な申告をすると税務署は見逃さない」ということも覚えておきましょう。
(参考:令和5事務年度 法人税等の調査事績の概要|国税庁)
(参考:令和5事務年度 所得税及び消費税調査等の状況|国税庁)
政府は2024年1月から、納付すべき税額が300万円を超える部分に対する無申告加算税の割合を30%に引き上げる税制改正を行っています(財務省 令和5年度税制改正より)。
| 状況 | 税額範囲 | 改正前の税率 | 改正後の税率(現在) |
|---|---|---|---|
| 税務調査の通知前 | すべて | 5% | 5% |
| 税務調査の通知後 | 50万円以下 | 10% | 10% |
| 50万円超~300万円以下 | 15% | 15% | |
| 300万円超 | 15% | 30% | |
| 税務調査後 | 50万円以下 | 15% | 15% |
| 50万円超~300万円以下 | 20% | 20% | |
| 300万円超 | 20% | 30% |
税務大学校の研究「無申告事案における重加算税の賦課要件」では、納税者が「隠ぺい又は仮装」して悪質な無申告を行った場合に課される「重加算税」は、その立証が非常に困難であるという指摘がありました。
無申告者自体、存在の把握は難しく、証拠となるような書類等を一切残していないことが多いため、多くの場合「単に失念していた」と理由付けするだけで故意であるかはわからないと言います。
そのため、無申告事案で重加算税が適用されず、15%の無申告加算税で済まされているケースが多い現状があると指摘しています。
この状態のままだと、「重加算税」という制裁措置の意義が損なわれるため、解決の手段として「無申告加算税」をより重い制裁措置とすることで無申告の抑止効果を高める狙いがあると言います。
上記に記載した通り、「期限後申告」では通常の納税に加えて「無申告加算税(または重加算税)」+「延滞税」という税金が上乗せされて請求されることがわかりました。
また、政府は監視の目を強化しているため、無申告であることはかなりまずい状況であることがわかります。
これらの税金は納付のタイミングによって金額が変わるので、申告忘れがわかった時点や税務署からの連絡があった時点で、直ちに税務署に出向いて申告を行う必要があります。
ただ、支払うことで生活が困るなど正当な理由がある時は支払いの猶予や分割納付を行うことが可能です(国税通則法 第46条)。
支払いや手続きに億劫にならずに、素直に申告・相談することが賢明です。

さて、ここまで読んで「よし、確定申告やってみよう!」と思った方のために、確定申告の方法を簡単に説明します。
初めての確定申告は不安かもしれませんが、一度やってみれば意外と簡単だと感じるはずです。
分からないことがあれば、遠慮なく税務署に相談してくださいね。
都道府県からアルバイトを探す(東日本)


確定申告の期間は翌年の2月16日から3月15日となっていますが、これを過ぎた後のお話です。
確定申告の期限である3月15日を過ぎた後でも確定申告は行うことは出来ます。
ただ、そこでの申告は「期限後申告」として扱われ、期間内に行う確定申告とは少し性質が異なります(国税通則法 第17条)。
それは、通常の納税に加えて「無申告加算税(国税通則法 第66条)」「延滞税(国税通則法 第60条)」という税金が上乗せされるというものです(国税庁HP:確定申告を忘れたとき)。
また、悪質な場合は無申告加算税に変わって、「重加算税(国税通則法 第68条)」が上乗せされることになっています。
これらの税率は期限後申告をどのタイミングで行うかでも大きく変わっていくので、その辺りを見ていきましょう。

最後に、アルバイトの確定申告に関してよくある質問をいくつか紹介します。
Q: アルバイトの収入が103万円を少し超えそう。どうすればいい?
A: 103万円を超えると扶養から外れる可能性があります。家族と相談して、働く時間を調整するか、確定申告の準備をしましょう。
Q: 確定申告の期限はいつ?
A: 通常、翌年の2月16日から3月15日までです。ただし、還付申告の場合は、この期間外でも5年以内なら申告できます。
Q: 確定申告って難しい?
A: 初めは少し複雑に感じるかもしれませんが、慣れれば意外と簡単です。分からないことは税務署に相談したり、ネットで調べたりしながら挑戦してみましょう。
Q: 確定申告で還付される金額の目安は?
A: 個人の状況によって大きく異なります。数千円から数万円程度が一般的ですが、中には10万円以上還付される人もいます。
都道府県からアルバイトを探す(西日本)


いかがでしたか?アルバイトと確定申告の関係について、少し理解が深まったのではないでしょうか。
確定申告は、一見すると難しそうで面倒くさい手続きに思えるかもしれません。
でも、実際はそれほど複雑ではありませんし、むしろメリットの方が大きいかもしれません。
特に、学生さんや若い方にとっては、確定申告は社会人としての第一歩を踏み出す良い機会にもなります。
税金の仕組みを理解し、自分の収入をしっかり把握することは、将来の経済的自立にもつながります。
もし確定申告が必要かどうか迷っている場合は、まずは税務署に相談してみるのがおすすめです。
専門家のアドバイスを受けることで、不安も解消されるはずです。
そして、もし確定申告が必要だと分かったら、ぜひ前向きに取り組んでみてください。
最初は大変に感じるかもしれませんが、一度経験すれば、次からはずっと楽になります。
アルバイトであっても、きちんと税金の申告をすることは、社会の一員としての責任を果たすことにもなります。
同時に、自分の権利を守ることにもつながるんです。
皆さんの頑張りが、より良い未来につながりますように。
確定申告、一緒に頑張りましょう!
この記事をシェア




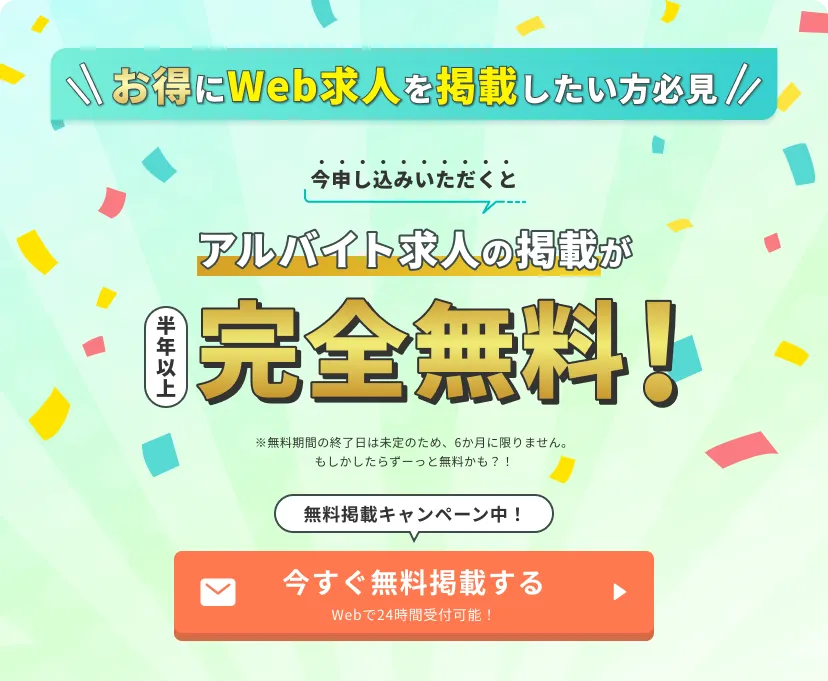
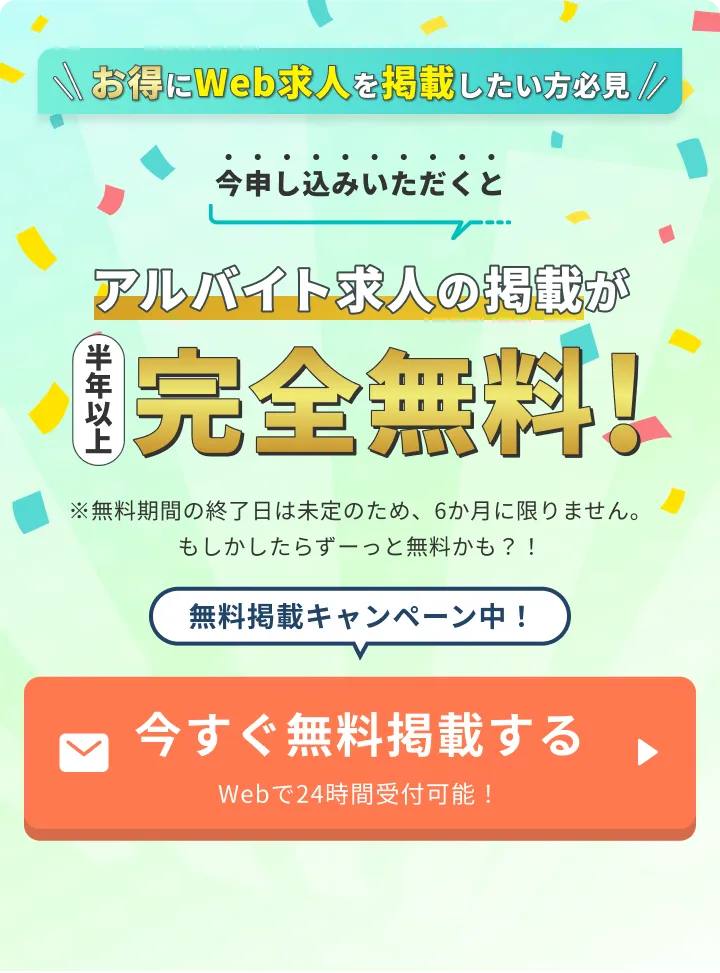




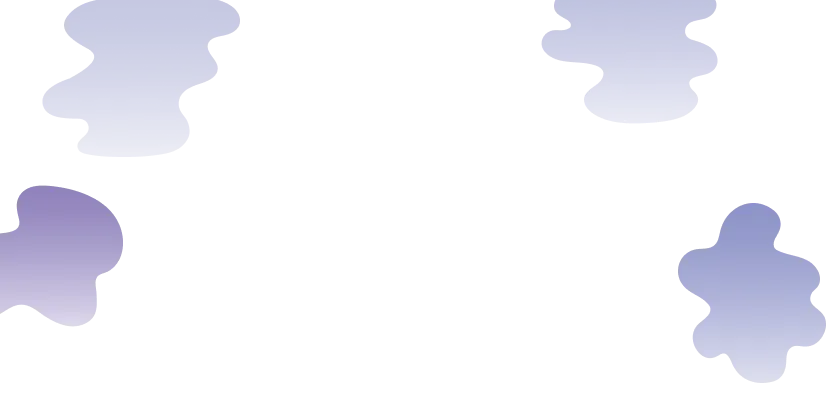
他のサイトは
掲載費用が高い
掲載しても
応募が無い
お店が忙しいので
採用の手間を減らしたい
長く続けてくれる人を
採用したい
欠員が出たので
スピーディーに
人員を補充したい
他のサイトは掲載費用が高い
掲載しても応募が無い
お店が忙しいので採用の手間を減らしたい
長く続けてくれる人を採用したい
欠員が出たので
スピーディーに人員を補充したい

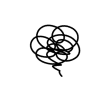

アルバイト採用のお悩み、



Point 1
半年以上無料で掲載可能!
採用コストの負担を最大限減らします!
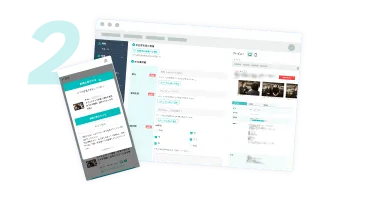
Point 2
わかりやすい管理画面でいつでも自由に求人記事を作成!
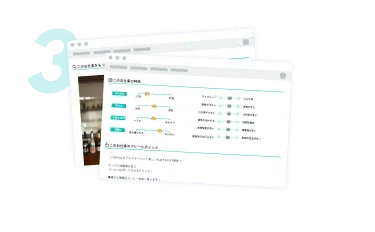
Point 3
お店の特徴や雰囲気・スタッフの人柄など、お店の魅力を多方面からアピール!
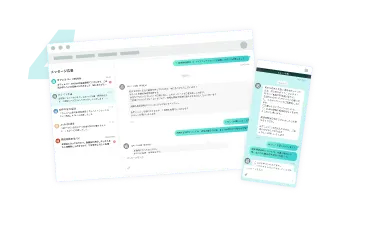
Point 4
独自のチャット機能でスムーズなコミュニケーションが可能!
お申し込み後は
すぐにご利用いただけます!
かかりません。 安心してご利用いただけます。
正社員募集もできますか?
雇用形態に関わらず、募集が可能です。
今、あるバイで求人掲載を
お申し込みいただくと
半年以上無料でご利用いただけます!
※無料期間の終了日は未定のため、 6か月に限りません。

あるバイで
バイトを探してみよう!

人気の条件から探す
都道府県を選択
条件を選択

スピード掲載可能!